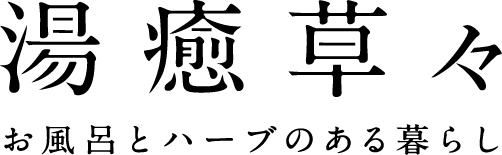読みもの

ハーブの香りで心までととのう、初めてのサウナ体験 / 各務原 恵みの湯
こちらのコラムでは、自分らしくナチュラルに暮らすためのポイントを、各務原の街の魅力と共にお伝えしていきます。まだまだ寒いこの季節。私の最近の楽しみは「サウナ」です!皆さんは、サウナに入ったことはありますか?お風呂ですぐのぼせる私は、「熱いから倒れるのでは?」「水風呂で心臓発作を起こしてしまうのでは?」と、サウナを怖がっていました。そんな私ですが、周りに勧められて1年前にサウナデビューし、いつの間にかサウナにハマるようになりました。サウナや銭湯は場所によって設備が違いますが、私のホームである各務原市の「恵みの湯」さんでの体験を元に、初心者目線から「サウナの入り方」をお伝えいたします。 はじめに・準備 水分補給&全身を拭く サウナ室は熱いけど怖くない 水風呂は最高に気持ちいい! 外気浴で「ととのう」 番外編・蒸気浴「ロウリュウ」 1.はじめに・準備 サウナは順番やコツなど「基本の入り方」があります。初めての方はぜひ予習をしてから入ってくださいね。まず、通常の銭湯と同じくシャワーを浴びて全身を洗います。体が冷えている場合は、軽くお風呂に浸かって温まりましょう。 2.水分補給&全身を拭くのが大切 サウナでは汗をたくさんかきますので、銭湯内にある水飲み場で水分補給をしましょう。その後全身をしっかり拭き、タオルもきっちり絞って、サウナ室へ。(薄手で吸水性の高いタオルがオススメです)全身をしっかり拭くことで汗が出やすくなり、周りへの配慮にもなります。 3.サウナ室は熱いけど怖くない サウナ室に入った瞬間は「熱すぎる!」「息苦しい!」とびっくりするかもしれません。でも大丈夫、落ち着いて。まずはタオルをおしりに敷き、もう1枚は頭にも巻いて、座ってリラックスしましょう。確かにめちゃくちゃ熱いですが、目をつむってじっとしていると、じわじわと全身から汗が出るのがわかります。汗がだらだら流れるようになり、脈が高くなり、体の芯まで充分に熱くなったら、サウナ室を出ます。私は7分ほどを目安にしていますが、体調に合わせて調整してみてくださいね。 4.水風呂は最高に気持ちいい! サウナ室から出たら、手桶で水を全身にかけて汗を流します。熱々の体に水をかけるなんて怖い!と思うかもしれませんが、両足、両腕、肩、顔、頭というように心臓から遠い場所からかけていきましょう。もちろん冷たいですが、躊躇せずに思い切ってかけるのがポイント。そしてそのまま、スルッと肩まで一気に水風呂に浸かります。ここでも躊躇せず、一気に入った方が逆に冷たく感じませんよ。 水風呂に入った瞬間は、冷たい・・・!と思うかもしれませんが、静かに目を閉じて体操座りをしていると、不思議と体全体にホワっとした「温かい膜」のようなものを感じるようになります。これはいわゆる「はごろも」と言われるもので、この温かい膜が水風呂の一番の心地よさです。ぜひじっくりと味わってくださいね。とはいえ、気持ち良くても水風呂では、体が冷えすぎる前に出るのがポイント。体の表面は冷えても体の芯は温まっている、それくらいの状態が一番心地よいので、私は30秒ほどで上がります。 5.外気浴で初めての「ととのい」へ 水風呂から上がったら、タオルで全身をきっちり拭きましょう。サウナの熱、水風呂の冷たさによる温冷交代浴で血行が良くなり、全身がほわ〜んとした不思議な心地よさに包まれていると思います。そのまま長椅子などに座って、数分間体を休めましょう。目をつむり瞑想すると、体がピリピリと心地よく痺れるような感覚になったり、頭がふわふわして浮遊感を味わったりできます。浴室内の椅子も良いですが、気候の良い時は露天での外気浴が最高ですよ。 サウナ→水風呂→小休憩の流れが、基本の1セットとなります。体調に合わせつつ3セットくらい繰り返すと、天にものぼる夢心地な「ととのう」体験ができます。サウナはこのセットが大切で、交感神経(温浴・冷浴)と副交感神経(休憩)を繰り返すことで血管が広がったり閉じたりし、血流が流れやすくなるり自律神経がととのいやすくなると言われています。 6.番外編:蒸気浴「ロウリュウ」で本格サウナ体験 恵みの湯さんでは、毎時30分に蒸気が出る「ロウリュウ」を体験することができます。蒸気により息ができなくなるくらい熱くなるのですが、熱いほど水風呂が気持ち良く感じられますので、サウナに慣れてきたらぜひ体験してもらいたいです。月替りでハーブやアロマの香りが変わるので、熱々のサウナ室が良い香りに包まれて病みつきになるはずですよ。 充分にサウナと水風呂を楽しんだら、そのまま浴室から出ても良いですが、少しお風呂に入って体を温め直すのもオススメです。恵みの湯さんでは、薬草ハーブの湯や、露天など、お風呂も充実しています。私はいつもサウナ後は、ハーブの香りに包まれながら寝転んで入れる「眠り湯」に入って締めることが多いです。最高に心地よいですよ。サウナは初めてという皆様、チャレンジできそうでしょうか?体調や気分に合わせて「自分らしいサウナ時間」をぜひ楽しんで、心地よい時間を過ごしましょう! 各務原 恵みの湯https://www.meguminoyu.jp/ 筆者:オゼキカナコ 岐阜県各務原市を中心に活動する店舗運営アドバイザー。...
もっと香りよく もっと温かく -煮出し編-
\ 当店オススメ /おうち風呂で、薬草ハーブのエキスをしっかりと味わう方法をご紹介。 お手軽にお試しいただけるものから、じっくり薬草ハーブを感じることのできる方法まで、楽しみ方は様々あります。ぜひご自身に合った方法を、お試しください。いつもより”もっと”素敵なバスタイムとなりますように。 point1 薬草ハーブ袋を投入するタイミング 薬草ハーブ袋をお風呂の沸かしはじめと同時にお風呂へ投入するのがおすすめです。湯に十分浸るようにします。沸いた後、少し揉み浸し、15分ほど湯になじませてから入浴します。湯に浸かる時間が長いほど、薬草のエキスは濃いものになります。お手軽に薬草ハーブをお楽しみいただけます。 ※ご注意いただきたいこと、長時間の入浴は、身体に負担がかかります。その日の体調に合わせて入浴時間を調整ください。また、入浴後は、色移りの可能性もありますので、入浴以後は、速やかにお湯を排水くださいませ。 point2 煮出して、薬草ハーブのエキスを濃厚に抽出 あらかじめ鍋などで薬草ハーブの袋をじっくり煮出します。ハーブの薬用成分が出た煮汁をお風呂へ投入(※入浴の際は、お湯を適温40℃前後であることを確認を忘れずに)。熱めのお湯の方が薬草ハーブのエキスが出やすく、少し手間はかかりますが、一番効果の高い方法です。 薬草ハーブ袋の作り方~煮出すまで >>すでに個包装されている薬草ハーブの時はこちらから 01.本日の薬草を選ぶ。 今回は ハーブの女王 とも呼ばれる岐阜県産「よもぎ」を使用。シングルハーブでもブレンドでもお好みのものをセレクトしてください。 02.薬草を粉砕する。 ミルやフードプロセッサーなど、薬草ハーブを細かくすることにより、よりエキスが抽出しやすくなります。 ※ご使用の前に 使用上の注意はよくお確かめいただいてから、使用してください。 03.不織布(もしくは布袋)に詰める。 袋の中で薬草ハーブが動けるようにぎゅっと詰めるより、隙間をあけて、不織布の上の方で固く結びます。中身が出てこないようにしっかりと結んでください。 04.たっぷりのお湯で、”煮出す”。 3リットルくらいのお水と、薬草ハーブ袋をお鍋に入れ、沸騰後弱火で5分ほどじっくりと煮出します。熱めのお湯の方が薬草ハーブのエキスが出やすいです。本格派の方は、30分煮出すとより濃厚なエキスが抽出されます。 05.いよいよお風呂へ 薬草ハーブ袋と煮出したエキスも一緒に、お鍋の中身をそのままお湯の中へ投入してください。熱くなりますので、入浴の際は、お湯が適温(40℃前後)であることを確認し、熱い場合は冷ましてから、入浴してくださいね。 ”もっと”香りよく。”もっと”温かく。植物の自然な香りは、からだを癒すとともに、私たちの疲れた心を穏やかに温めてくれるでしょう。...

自宅のお風呂で、免疫力を高める「冬のHPS入浴法」を実践しよう!
様々な病気の原因にもなる免疫力の低下を防ぐため、自宅のお風呂でもできる免疫力UPの入浴方法を医学博士、ヒートショックプロテイン研究者でもある伊藤要子先生に教えていただきました。 HSP(ヒートショックプロテイン)とは HSPとは、さまざまなストレスから私たちの体を守ってくれる、ほとんどの生き物が備えている能力(たんぱく質)です。例えば、元気のないレタスを50℃のお湯にしばらく浸すと、シャキッとしたレタスに戻ってきます。これは、まさしくHSPの仕業。熱ストレスにより、HSPが増加し酸化を防御し、鮮度が甦ったということです。 私たちの体を作る細胞は、水分を除けばほとんどがタンパク質です。HSPは、ストレスにより構造がおかしくなったタンパク質を修復して元気にしてくれる素晴らしい存在です。そのHSPを自身で増やし、自己回復力を向上させることで、病気の予防や美肌へつなげ、健康に役立てることができるのです。 冬に必要な免疫力を高めるHSP ちなみに、ストレスとは精神的ストレスだけではありません。ウィルス感染、熱ストレス、病原菌、紫外線など、私たちが心や体に受ける すべてのダメージのことをいいます。 気温の変化や乾燥しやすい湿度がウィルスの至適な環境を作りやすい冬。ウィルス感染や病原菌からカラダを守る対策として、また、油断しがちな冬の紫外線ストレスによる肌のシミ、シワ予防など美肌にも効果があると言われています。 ストレスから脳(海馬)の神経細胞を守るHSPが、うつの予防と治療の両面で活躍します。 HSPの免疫増強作用 免疫作用を担っているのは、血液中の白血球です。細菌やウイルスに感染した細胞は、白血球の一部であるリンパ球(B細胞・T細胞)によって攻撃されるため、ウイルス感染防御にはリンパ球が大変重要になってきます。HSP入浴法は、このリンパ球を増加させることができるので、 ウイルス感染防御に大変有効です。手洗い、うがいはもちろんですが、やはり自分の免疫力を高めることが重要な時です。 自宅のお風呂で、HSP入浴法を実践し免疫力を高めましょう! HSP入浴の方法 【準備するもの】 飲料水:大量の汗が出るので、必ず飲料水を準備しましょう。特にのぼせやすい人、汗が出にくい人は入浴前にも水分をとっておくとよいでしょう。 防水タイプの舌下型体温計 防水温湿時計(時計と温度計(室温)や湿度計も一緒についているのが便利) 湯温計 【入浴前】 湯温の設定:冬は外気温が10℃以下と寒く、体表温度も低くなるため、湯温は41~42℃が適温です。 入浴前に浴室内を温めておきます。浴室用の暖房があると便利ですが、お風呂のふたを開けておいたり、熱めのシャワーで浴室内を温めるとよいでしょう。 脱衣室を暖房器具で温めておくことをおすすめします。特に冬の入浴事故は、急激な温度差によることが多いので、特に高齢な方は注意が必要です。 湯船に入る前に手や足など、心臓に遠い部位からしっかりと何度もかけ湯をしてください。 【入浴法】 ・入り方 まずは、半身浴から始め、ゆっくりと心臓まで浸かります。さらに、肩まで浸かる全身浴へ。体温を38℃以上または、 体温を1.5℃以上上げるよう、時々体温を測定しながら入浴するとよいでしょう。入浴時間は、15分前後を目安にしてください。冬場は、外気温が低いため、体温が上がりにくい傾向にあります。自身の様子をみながら時間を調整してください。 決して無理はしてはいけません。つらいと感じたら、我慢せず湯船から出てください。 冬場は入浴中に湯温が低下しやすいため、浴槽の蓋を首元近くまで持ってくるとよいでしょう。湯温が低下したら、追い焚きをして湯温を調整してください。 高齢の方、体力に自信の無い方は、心臓に負担の少ない半身浴がお勧めですが、冬場は肩が冷えるのでご注意ください。...

冬の身体を温め癒す和ハーブー大薬王樹“ビワ”ー
冬におすすめのハーブのひとつがバラ科の“ビワ”。今回は、和ハーブインストラクター半谷美野子さんにご自身の経験をもとに"ビワの葉"についてお話いただきました。 ビワといえば果物ですが、和ハーブ※として注目したいのは葉と種。生薬名はビワヨウ(枇杷葉)といい、民間薬としては種子も活用されています。葉はお茶やチンキ、温湿布にしたり、濃く煮だして入浴剤や染め物にも使ったりと、活用用途がいっぱい!何からご紹介すればいいかわからないほど、カラダにいい効果があると言われているビワですが、まずは歴史からご紹介していきたいと思います。 *和ハーブとは、一般社団法人 和ハーブ協会 https://wa-herb.com/waherb3/waherb3/ では、「和ハーブ」を「在来種(日本原産)、あるいは江戸時代以前より日本に広く自生している有用植物」と定義しています。 ビワの歴史 ・三千年の歴史 ビワは中国の古い仏典「涅槃経」の中に登場し、「ビワの木には、枝や葉、根、茎すべてに大きな薬効があるので、病気の人は手で触れたり、香りを嘆いだり、舌でなめることによって、すべての病苦を治す。」「生きとし生きるものの万病を治す植物」といわれ、“大薬王樹”と書かれているそうです。 ・日本には仏教と共に伝来 さて、ビワは古くからありますが日本在来の植物ではなく、奈良時代に仏教とともに原産国の中国から伝来したといわれ、“正倉院文書”にもビワについて記載されています。 江戸時代に流行ったのが、「琵琶葉湯」。ビワの葉に7種類の生薬を配合した暑気払いの飲み物で、重宝されたそうです。 私の実家にはビワの木が植えてあって、小さい頃から実を食べ、ビワの葉茶を飲んで育ったのですが、「ビワを庭に植えるのは縁起が悪いので、本当は植えない方がいいといわれているんだけどね。」と母や祖母から聞いていました。でもこの話、実は江戸時代の琵琶葉湯売りが自分の商売のために、「ビワの木を植えると病人が出る」などと流布したという説があることを知り、我が家の庭にはビワを植えています。 ビワの葉の採取について さて、なぜ冬におすすめなのか?という理由のひとつがビワの葉は一年中採取し、活用できるのですが、一説に大寒の時季の葉の薬効が高いといわれているため。染め物も冬の葉で染めたものの色が一番濃いそうです。 私は冬にゴワゴワして、濃い緑色で一年以上はたっている古そうな葉をまとめて摘み取ります。よく洗って、お茶や入浴剤にしたり、化粧水や虫刺され用に生のままホワイトリカーにつけてエキスを抽出してチンキ*にして保存しています。チンキの作り方は、後ほど、、、 また、11月末~1月頃に咲く花に出会うのも採取時の楽しみのひとつ。白い花はかわいらしく、なんともいえない上品な香り。冬の寒さから身を守るために毛に覆われた丸い蕾も、虫たちのご馳走になる蜜を蓄えた花も是非みなさんに見ていただきたいです。 ビワの花 ビワの葉染めとビワの葉採取 ビワの葉の薬効 ・風邪の時に ビワの葉は抗炎症作用や抗菌作用が高く、咳を鎮めたり、痰を除いたり、胃を丈夫にするなど、冬の風邪にありがちな症状を鎮める効能が色々あるのも冬にビワが活躍する理由のひとつ。 我が家では風邪をひいたら、ビワの葉を煮出したビワ茶*をまめに飲み、喉が痛い時はお茶やチンキでうがいをします。漢方処方だと「辛夷清肺湯(しんいせいはいとう)」に配合され、鼻づまりの解消や鼻の炎症を鎮めるために用いられるそうです。 ビワの葉茶は、一晩おくと赤色に。染色するときも、一晩おくとキレイな色に染まります。 ・お風呂に また煎じ液やチンキは様々な美肌にもよいといわれていますが、浴用としても使えるのです。とても寒い飛騨に住む友人から「色々な薬草をお風呂に入れてきたけれど、ビワの葉を煮出したら、身体が芯から温まってよく眠れるので、冬にビワの葉は欠かせない」と聞き、試してみたら、身体がポッカポカに!手浴や足浴にもおすすめです。 ・ビワの葉蒟蒻温湿布 傷み・かゆみ・炎症を抑える効果がある“アミグダリン”の含有量が多いのもビワの葉の特徴。生の葉のツルツルの面を気になる症状の場所にに当てたり、チンキや煎じ液をつけてる方法で救われた方が沢山いらっしゃいます。 特に冬、冷えなどが辛い時や風邪をひきそうな時に、試していただきたいのが、ビワの葉蒟蒻温湿布。...

しっとり美肌、贅沢な日本酒風呂であったまろ
我が家では、毎年元旦の初風呂は「日本酒風呂」を楽しんでいます。実は入浴剤としても使用できる日本酒。お風呂に入れて大丈夫?酔わないの?と思われるかもしれませんが アルコールが苦手で一切、お酒は飲めない私ですが今まで一度も酔ったことはありませんし、肌が荒れることもありませんでした。日本酒の効果で肌もしっとり、身体もすごく温まるので、寒くて乾燥する冬にはとてもおすすめですよ。 もくじ ・日本酒の選び方 ・日本酒風呂のよいところ ・使用する日本酒の量はどれくらい? ・日本酒風呂の入浴法 ・日本酒風呂で注意したいこと 日本酒の選び方 お風呂に入れる日本酒は、高価なものでなくても大丈夫です。飲み残しでも問題ありませんが、アミノ酸を多く含む「純米酒」と呼ばれる、原材料に「米、米こうじ」と書かれたお酒を選ぶとよいでしょう。 日本酒に含まれるアミノ酸は、美容によい成分が含まれており、天然保湿因子やコラーゲンを生成することが多くの研究で明らかになっています。乾燥からくるお肌のかゆみや女性に大敵のシワやたるみにも効果がありそうですよね。 日本酒風呂の良いところ ☆アミノ酸による美肌効果 ☆こうじ菌による美白効果 ☆日本酒の成分による血行促進効果 ☆日本酒のマイナスエネルギー浄化効果 美肌、美白、血行促進、浄化効果もあるなんて良いこと尽くしの日本酒風呂。 早速、今晩のお風呂で試してみたくなりましたね。 使用する日本酒の量はどれくらい? お好みになりますが、お風呂のお湯 約200リットルに対し、300~500mlが適量です。最初は、コップ1杯程度でも大丈夫です。私は、たいてい300ml程度の量で楽しみます。 日本酒風呂の入浴法 お湯の温度は、冬場は40~41度前後のお湯をおすすめします。夏場は、38度前後がよいでしょう。 日本酒風呂には血行促進作用がありますので、とてもよく温まります。健康な方は、肩までしっかり浸かる全身浴を10~15分ほど行うとよいでしょう。疲労回復効果も期待できます。温まりが足りないと思われる方は、最後の1~2分だけ追い焚きをして温まりを実感すると満足できるでしょう。最初からお湯の温度を上げすぎると、身体への負担も大きいですし、心身が興奮してしまうためリラックス効果が得られずおすすめできません。 日本酒風呂で注意したいこと アルコールを全く受けつけない私でも日本酒風呂は、問題なく入浴できます。日本酒を500ml使用した時も体調が悪くなることはありませんでした。皮膚から日本酒の成分を吸収するのですが、吸収しすぎることはないためと思われます。 しかしながら、これには個人差がありますのでアルコールに弱い方や妊婦さん高齢の方は十分ご注意ください。最初は少量から始め、様子を見ながら入浴するようにしましょう。また、小さなお子さまはできるだけ避けるようにしましょう。...

からだの芯から温める生姜でぽかぽか、インドの本格チャイで免疫力を上げる
身体の冷えは万病の元とも言われ、免疫力の低下や自律神経が乱れるなど、様々なからだの不調が現れます。今回は、からだを温める作用のある生姜使ったインドのカルティカさん直伝ジンジャーチャイの作り方を紹介します。