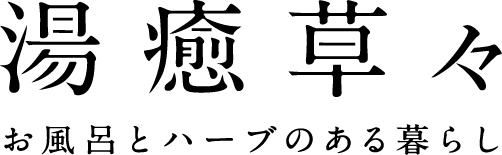読みもの

より良い眠りのための入浴法
新しい季節を迎え、今までとは違った環境での生活がスタートした方も多いと思います。環境の変化にともない、心身ともに緊張されている方も多いのではないでしょうか。今回は、心身の緊張を解きほぐし、良い眠りへ誘う、入浴法と入浴後の過ごし方をご紹介します。 ノンレム睡眠とレム睡眠 さわやかな朝を迎えるためには、質の良い睡眠がとても大切です。睡眠には、ノンレム睡眠(脳のための睡眠)とレム睡眠(身体の睡眠)があります。 入眠時には、まずノンレム睡眠が現れ、続いて1時間から2時間ほどでレム睡眠に移ります。以後、二つの睡眠を90分サイクルで交互に繰り返しますが、大切なのは最初のノンレム睡眠の90分。ここの眠りをいかに深い眠りにするかがポイントとなります。 それには、お風呂に入るタイミングも大きく関わってきます。 お風呂に入るタイミングと快眠入浴法 人は体温が下がり始めるときに眠くなります。よって、就寝時間の2時間前には入浴を始めると良いでしょう。 入浴の際は、40℃前後のお湯に10~15分間 浸かるリラックス入浴を心がけます。この時、熱めのお湯に浸かってしまうと元気信号でもある交感神経が高くなり、眠りを遠ざけてしまいます。 40℃のお風呂で温まりが足りないときは、最後の1~2分だけ追い焚きをして、温まり感を高めるのも良いでしょう。20分以上の長風呂も避けた方がよいです。 入浴後の過ごし方 そして、お風呂あがりは急に身体を冷やさないようにするのもポイントです。脱衣所を温めておく、浴室内で身体についた水滴を拭きとるなど、体温低下を避ける工夫をしましょう。 お風呂あがりは、リラックス感を高め入眠を促す作用をもつ、カモミールやペパーミントのハーブティーで水分補給をすることをおすすめします。粘液質※のあるハーブと合わせて、のどの潤いもカバーしていきましょう。 ※多糖類から成る水分を吸収すると膨張し、オクラのようにねばねばとした性質のこと また、入浴後はビタミンCやミネラルも不足するため、ローズヒップやネトルなどビタミンやミネラル豊富なハーブとのブレンドもおすすめです。 お風呂のあとにおすすめのブレンドハーブティー カモミール×リンデン×カレンデュラ カモミール×ペパーミント×マロウブルー レモンバーム×ペパーミント×ネトル ダンディライオン×ローズヒップ×パッションフラワー このブレンドを参考にご自身の好みで、ブレンドを調整してみるのも楽しいですよ。 ほんの少しの気遣いで、眠りの質が大きく変わります。明日も元気に過ごせるよう、お風呂と睡眠の時間を大切にしてください。 CHIHO.hoshiyama ハーブ&バスセラピスト® 岐阜各務原にある創業25年の風呂屋「恵みの湯」で人気の岐阜産”伊吹薬草湯”に自身の不調を支えられた経験より、日本古来から伝わる植物浴の素晴らしさを多くの人に実感してもらいたいという想いからHERB&BATHプロジェクトを始動。入浴で身体を温める大切さを伝えるバスセラピストとして、植物の活用を広げるハーバルセラピストとして活動中。また、自社ハーブ農園にて農薬を使用せず様々なハーブを栽培しています。温泉入浴指導員温泉ソムリエマスター JAMHA認定ハーバルセラピストJAMHA認定ハーブ&ライフコーディネーターJAMHA認定メディカルハーブコーディネーターJAPHY認定...

ハーブとスパイスの料理を使ったケアするカフェ -Medi Café さんを訪ねました- 前編
愛知県江南市のショッピングモール隣、住宅の一角にある白い可愛らしいカフェ。2017年10月にハーブ&スパイスのカフェをオープンされて3年目を迎えます。 Medi Cafe オーナー山田真代さんにフードコンサルタントのひらつかが、お店作りやハーブとスパイスの料理へ想いをお聞きしました。今回、前編と後編に分かれてお届けします。前編は、お店やお料理の想いとハーブとスパイスの関わりについて、後編はお店の紹介についてです。 実は、2年くらい前だったかインスタで見つけてずっと追っていたんです。なかなか伺う機会がなかったのですが今回お会いできて嬉しいです。ハーブ&スパイスのカフェをしようと思ったキッカケはなんですか? 実は、私自身が精神的に病んで、引きこもっていた時期があったんです。その時にハーブティーを飲んだらすごく気持ちが楽になった経験から、なんかいいんじゃないかと思って、ハーブの勉強を始めました。 ハーブティーもとても良いけど、ご飯の中に取り入れる方が自然に食べられるし、カラダにとっても得をするというか…もっとカラダにいいよね。ということからお食事も楽しめるカフェにしたんです。 なので、オシャレなハーブカフェっていうよりも病んでる店主のハーブカフェというのがコンセプトでもあるんです(笑) おひとりさまとかお疲れの人の居場所となったらいいなと思って。家も嫌ってなったときに居場所って意外となくて。 わたしが病んでた時期、賑やかなカフェにはハッピーな人がいっぱいいて辛いし、私自身もひとりでショッピングモールの隅っこで泣いてたことがあったんですね。だから、お店の作りもカウンター席を多めにしたりしているんです。 おひとりで来られてちょっと元気のない人とかとお話しされたりもするんですか。 そうですね、心のバランスを取ってくれるようなハーブティーをおすすめしたりしています。薬飲んだり、心療内科行ったりとか…私自身が経験あるので、人には言えないお悩みにも寄り添えるかなと思います。 SNSでもご自身の経験を赤裸々にお話しもされたりするんですね。 そうなんです(笑)。お店の運営としては賛否両論あると思うのですが、心身のお辛い方がなかなか自分から心療内科に行ってるとは、言えないと思うんですよね。なので、自分の経験を発信して、気楽に来てもらってお話ししやすいようにしたいな…と思ってるんです。誰もがハッピーな状態ばかりではないし、疲れちゃうことなんてみんなあるんですよね。 そうですよね、お料理もハーブとスパイスがテーマということですが何か気をつけていることとかありますか。 ハーブもスパイスもですが、苦手意識が多い方がいらっしゃるんですけど、生姜とかニンニクだってスパイスだし、料理の中に自然に摂り入れるようなことをつねに考えています。 「使っているけど食べれるでしょ」っていう感じで、ここで食べたことで苦手意識を克服するキッカケになったらいいなと思います。 ハーブもスパイスも食材にいろんな作用があると思いますが、調理方法としてどのような活用をされていますか。 だいたいのお料理にハーブ入れているんですけど、味は主張しないけど実は入っていたりとか、風味付けとか色を付けるとか。調味料を使わなくてハーブでいけるのであれば、ハーブを使うとか。 例えば酸味を出したい時には、ハイビスカスとかコクを出すなら根っこ系のハーブを使うとか。出来るだけハーブやスパイスを使って風味を出すような工夫をしていますね。 食材のこだわりはありますか。 メインで使うお肉やお魚は国産に拘っています。野菜は自家製で、実家の父に協力してもらって作ってもらっています。私も日曜には必ず岐阜の畑へ行って収穫や、世話をしに行っています。自家製の野菜で間に合わないときは購入もしますが、その時も出来るだけ地元野菜を仕入れるようにしています。 自家製や地元野菜となると旬のものになりますね。季節によっては同じ野菜が続いたりとかもしますよね。 そうなんです。白菜ばかりとかキュウリが続くとか、今は大根が山盛りです(笑)。これも調理方法やスパイスで変化を出しています。そうすると、お客さんからこれどうやってやるのと聞かれたり、逆に教えてもらったりして会話が生まれたり、料理のバリエーションの幅も広がるので、それもいいのかなと思っています。 メニューが日替わりカレーとか気まぐれランチとありますが、スパイスの調合とか大変じゃないですか? 同じ味にするのが苦手なんです(笑)その日によってムラがありますし、いつも同じだと私自身が飽きてしまうし、いろいろやりたい気持ちも出てくるので日々実験です。...

一年中楽しめる!一番身近な和ハーブ「ヨモギ」
身近な和ハーブの代表として、一番に思い浮かぶヨモギ。 食べてよし、飲んでよし、浸かってよし、塗ってよし、嗅いでよし、燃やしてよしの5拍子揃ったハーブです。ヨモギには様々な種類があり、一年を通して様々な形で使うことができます。今回は、ヨモギの見分けかたと使い方をご紹介します。 春には、白っぽい緑色の若葉が出始めるヨモギ。 ヨモギはキク科のヨモギ属。ヨモギの仲間は日本に30種類以上あります。一般的によもぎ餅やお茶などで使われるヨモギは「カズサヨモギ」と呼ばれるものです。 ほかにもお灸の艾(もぐさ)にするものは「オオヨモギ」。 沖縄で“フーチバー”と呼ばれ、沖縄のスーパーや市場でも購入できる「ニシヨモギ」があります。 沖縄では、ジューシー(炊き込みご飯)やヤギ汁などにも使用されています。私はニシヨモギの雑炊をいただいたことがあります。香りがよく、苦みも少なくて、とても食べやすいヨモギでした。 また河原や海岸の砂地に生える「カワラヨモギ」の乾燥した花穂は茵蔯蒿(いんちんこう)という名の生薬として漢方薬にも使われています。 そして、ハーブの世界で「マグワート」と呼ばれているのは「オウシュウヨモギ」のことを言います。 私たちに一番身近な「カズサヨモギ」 ・カズサヨモギの見分け方 ・ヨモギの効果 ・ヨモギの使い方 ヨモギの香りはするか? 野草を見分ける時にとても大切なのが“香り”。 食べる野草を摘む時に目だけで判断するのは危険なことがあります。ヨモギの若葉は、猛毒トリカブトと似ているといわれていますが、トリカブトにはヨモギの香りはしません。 ヨモギの葉を摘んだら、ヨモギの香りがするか、必ず揉んで香りを確認してみましょう! 葉の裏に白い毛は生えているか? ヨモギの葉の裏には必ず、お灸のモグサ(艾)の材料になる白い毛が生えているので、目と触感でチェックしましょう。 托葉はついているか? ヨモギは葉の付け根に“仮托葉”(たくよう)という小さな葉がつくのも特徴です。若葉の時しか見分けがつかないという方は、仮托葉を確認してみてください。 ヨモギの効果 クロロフィルやタンニンのほか、有効成分の宝庫のヨモギは乾燥したものだけではなく、生葉も大変優れています。指を切って、血が止まらない時に揉んでつけたら血が止まったことや、私の講座に参加されていたお子さんが腕を毛虫に刺されて発疹が出た時に生葉を揉んでつけて、手ぬぐいで巻いておいたら15分ぐらいで落ち着いたことがありました。 一般的な効能としては、生葉を揉んで貼ると、止血のほかにも虫刺され、切り傷、打撲傷や腫物。煎じて飲むと強壮、健胃、去痰、止血、腹痛、風邪、食中毒、冷え性などほかにも色々な効能があるといわれています。浴湯料としては、あせも、冷え性、腰痛、リウマチ、美容などにもよいそうです。(出典「食べる薬草事典 春夏秋冬・身近な草木75種」村上光太郎 著)...

わたしがサウナにいく理由「エスキース ドローイング サウナ」
あなたのサウナに行く目的は何でしょうか。ととのいを求めて、汗をかいて運動感覚、美肌つくりのため、流行に便乗… 私のサウナに行く目的、それは「エスキースとドローイング」です。 現代美術家である私の、絵画を描く時の手順として大きく3つがあります。 それは、頭の中を文字として書き出しコンセプトとして洗いだす「エスキース」とその言葉や断片的なイメージの羅列から具体的なモチーフや構図に変換していく「ドローイング」。「エスキース」と「ドローイング」から実際キャンバスに絵の具を落とし画面上にできた偶然の色の重なりや広がりから発想を広げ絵づくりを進めていく「デカルコマニー」があります。 自分が誰かに伝えたいけれど言葉では足りず角が立つ色々な思いを、言葉以上に強く優しく芯まで他の人に伝わり揺さぶれるように具体的に客観的に自分自身を解体して知ってく大切な手順です。 そもそも自分を知るとは何でしょう。自分自身とは、いま、ここに、いる、じぶんは、どういう生き物でしょうか。私が思う「じぶん」は、常に疑問で、つかんだと思っても消える湯気のようです。ないものを形にし組み立て整理していく作業をする上で必要となってくるのは、思考の明瞭化。 サウナは、温冷交代浴と休憩により交感神経と副交感神経の動きを正常化し、心身のあらゆる部位に良い影響をあたえてくれると言われています。もやもやと断片的な思考が散らかった状態でサウナへ入り熱さや室内の香り、汗の出具合に向かい、無の状態へと導かれます。あつい、もう少し、あつい…、そして全身が冷たさを求めるタイミングで水風呂へ。冷たい水に包まれて頭の芯がすっと冷えていく。同時にサウナに入る前、散らかっていた頭の中がすっ…と静かになっていることに気づきます。身体を拭いて椅子に横たわり静かに目を閉じて、全身の毛細血管がどくどくと脈打つのを感じながら、感覚に触れる一つ一つを読み解いていく。これは、一部のサウナ愛好家に「サウナブースト」と呼ばれる、思考が明瞭化し仕事がどんどんはかどる状態です。この状態で私は絵画の構想を練ります。 今自分が強く感じていること、それは何か。どうして、どこが引っ掛かり、なにが重要で、何に似ているか。モチーフ、言葉、構図、色彩、断片的な絵画の破片がどんどんと出てくるのはサウナで蒸されるとき。水風呂で身体も頭も冷やし一度白紙に。 出てきたものを落ち着いて順番に精査し、持っていく先を具体的に頭の中でつくり込み、構成ができるのは外気浴やぬるめの露天風呂です。 (頭の)整理がついた、と感じるタイミングと汗と老廃物が出し切れた感覚が得られるのは大体同じくらい。サウナを出て忘れないうちに紙に書き出し、画面作りに進みます。 ひたすら紙に向かうことや、携帯のメモ機能やSNSでのつぶやき、料理で細かな仕込みをすることや、庭で黙々と日光を浴びながら雑草を抜くことも、思考を明瞭化し「エスキースとドローイング」としては効果的です。 しかし、サウナはそれらのどれよりも”確実に”、”効果的に”脳の働きをよくしてくれます。 サウナスパ健康アドバイザーの勉強をしていますが、それらの知識や効果を知ってしまった以上、サウナ以外の思考の場が設けにくくなったのは問題に感じています。笑 実はこちらのコラムのお話をいただき構想を練ったのもサウナです。書く前にも我らがホーム「恵みの湯」でしっかり”2ロウリュウ”してきました。 (恵みの湯では1時間に1度オートでアロマロウリュウをしています。サウナに入った長さを示す単位にロウリュウを使いがちです。) 定期的に行われる「生ハーブ」によるロウリュウは、アロマウォーターとは違い、天然の香りが自然を強く感じさせてくれて、サウナ内では本来活躍することのない嗅覚が刺激されるのも、思考の幅をより広げてくれていると感じます。 サウナの日、恵みの湯では #サウナフェス で「自分でえらぶ生ハーブロウリュウ」が体験できます。 好きな香りを自分でえらび、感じながらのととのい体験ができるのは、贅沢ですね。 最高のサウナブーストができそうです。自分自身を知るためのサウナを試してみてください。 澤田摩耶 現代美術家 香川県出身 日常の中に変化が生まれる瞬間の閃きを油彩で描く。岐阜県各務原市に移住し、恵みの湯WEBスタッフとして在籍中。ハーブやサウナのある暮らしに心酔し、口を開けばサウナイキタイ!公式Instagram https://www.instagram.com/maya_s_kaitano/

花粉の季節に気をつけたい、お風呂の入り方
花粉と上手に付き合うためにお風呂を活用 花粉症は、花粉によって起こるアレルギー症状で自身のもつ免疫の過剰反応が原因です。 日本では、スギやヒノキが一般的ですが、イネ科の植物やキク科のブタクサ、カモミール、ヨモギなどが原因でアレルギー反応を起こす方も多くいらっしゃいます。花粉が体内に入ることにより、鼻水が出たり、目や肌などにかゆみが出たりといった症状が続きます。 花粉症のつらい症状を緩和させるには、できるかぎり体内に花粉を入れないことが大切です。そのためこの時期は、帰宅後早めの入浴を心がけ、髪や体についた花粉を素早く洗い流しましょう。 お風呂は、花粉症の人にとって最高の休息場所 特にひどい鼻づまりには入浴がとても効果的です。温熱作用で血流が促進し、一時的に鼻づまりが緩和します。また、入浴すると自然に湯気を吸うため、鼻の内部に入った花粉を洗い流すことができます。 さらに、お風呂の湯気は喉にも良い効果が。せきやたんで喉が辛い時も、湯気の潤いで気道が広がり楽になります。この季節はシャワーより、お風呂に浸かることを心がけると良いですね。 蒸気吸入・フェイシャルスチームもおすすめ! 蒸気吸入やフェイシャルスチームは、自宅で手軽にできますので、気分転換にもおすすめです。 ボウルに、ペパーミントやユーカリのドライハーブを適量入れ、熱湯を注ぎます。頭からバスタオルをかぶり、目をつぶり、水面より 30 ㎝~50 ㎝ 離れたところで立ち上がる蒸気を吸入します。この時、洗面器に顔を近づけすぎると肌を刺激したり、やけどをしたりすることがあるので、十分に注意をしてください。 リフレッシュできるとともに、鼻やのどが潤い、一時的に症状が和らぎます。 アレルギー症状の時にやってはいけない入浴とは シャワーやお風呂の湯を熱くしすぎないこと。42℃を超える湯で入浴すると、アレルギー症状を悪化させるヒスタミンという物質が生まれることが研究で分かっています。(最高の入浴法 P128 著者 温泉療法専門医 早坂信哉) 最適な入浴温度は、40℃くらいのぬる湯。入浴時間は15分程度にしましょう。 花粉症の人にとって「お風呂は最高の救世主」毎日のお風呂を有効に利用して、辛い時期を乗り切りましょう!! CHIHO.hoshiyama ハーブ&バスセラピスト® 岐阜各務原にある創業25年の風呂屋「恵みの湯」で人気の岐阜産”伊吹薬草湯”に自身の不調を支えられた経験より、日本古来から伝わる植物浴の素晴らしさを多くの人に実感してもらいたいという想いからHERB&BATHプロジェクトを始動。入浴で身体を温める大切さを伝えるバスセラピストとして、植物の活用を広げるハーバルセラピストとして活動中。また、恵みの湯ハーブ農園にて農薬を使用せず様々なハーブを栽培しています。温泉入浴指導員温泉ソムリエマスター JAMHA認定ハーバルセラピストJAMHA認定ハーブ&ライフコーディネーターJAMHA認定メディカルハーブコーディネーターJAPHY認定 ハーブティーソムリエouchi...

ストレス や 心のモヤモヤ 春へと向かうわたしたちの心身を整える ハーブ
人類は進化していく過程で、常に植物の力を借りてきました。古くは民衆の心をしずめるために、さらには病める人の治療薬として、また食卓を豊かにする調味料や保存のための殺菌剤としての役割も果たしてきました。 近代になり科学が進歩し、薬をはじめ、ありとあらゆるものが合成可能となった社会では、人は植物との結びつきを忘れたかのように暮らしていますが、人は植物なしでは生きていくことができません。 いつの時代も人に力を与え、疲れを癒してくれるのは植物を含む大自然、そこに近い場所にいるほど健康に近づくと考えられますが、都市部でそれはなかなか難しいですよね。 植物を身近に生活することが難しい方は、部屋に1鉢植物を置いてみましょう。小さなもので構いません。 日々の中に生じるちょっとしたイライラやモヤモヤは、心身に思った以上の負荷を与えています。1日の終わりに心とからだの様子を眺め、違和感を持つ部分があったら早めのケアを。植物の力を借りて、整えていきましょう。 からだへと関心を向ける 折しも2月の立春からは暦上では春とされ、四季の立ち上がりを迎えています。草木の芽吹きと同様に、冬の間、停滞気味になっていたわたしたち人の細胞も少しずつ活発になっていきます。 その動こうとする力に身体が対応しきれていない時に起こるのが、めまい、無気力、不安感、不眠などの自律神経系にまつわる不調です。例年2~3月の体調について思い当たる方もあるのではないでしょうか。 ロシアのスポーツ選手や宇宙飛行士が体力維持のために飲用していたことで知られる「エゾウコギ」というハーブは、別名シベリア人参とも呼ばれ、神経系、免疫系、ホルモン系などあらゆる機能を高め(=アダプトゲン作用)、この時季の体調管理や感染症の予防にも役立ちます。他に風味の良いハーブティーとして近年人気のホーリーバジルにも同様の働きがみられます、これらを活用してみて下さい。 エゾウコギ 科名:ウコギ科 使用部位:根、根茎、茎 活用法:ハーブティー(ドライハーブ2~3gに熱湯を注ぎ、5~10分蒸らす)チンキ剤にしても 花粉症へと対応するハーブ 日本気象協会によると2021年の花粉飛散量について、九州から関東おいては前シーズンより多いとの予測がされています。 鼻がぐずぐずする時にスッキリするハーブは、エルダーフラワー、ルイボス、ペパーミント、ネトルなどいくつか挙げられますが、その中でもオススメなのがペパーミントです。 お湯を注いでティーにすると、スッとした香りが蒸気と共に立ち上り、辛い鼻のぐずぐずがいくらか楽に感じられます。また爽やかな香りは気分もスッキリさせ、実は優秀なメディカルハーブとも言われています。 栽培も簡単ですので、一家に1苗、常備されるといいのではないでしょうか。ミント類には様々な種類がありますが、ペパーミントがおすすめです。苗をお求めの際は、間違いのないようにして下さい。 ペパーミント 科名:シソ科 使用部位:葉使用法:ハーブティー ハーブ2~3gに対し熱湯150mlで5分抽出。チンキ剤 ペパーミントの抽出には度数40%以上のアルコールが望ましい。 飲用の他、マウスウォッシュとしても活用できる。 栽培: 強い乾燥が苦手、プランター栽培時は水切れに注意する。 収穫: 若い葉を摘み取る。(蕾や花をつける頃は風味も効能も劣ります) 最後に一言… 人に本来備わっている健康や美しさを引き出すのは、日々の積み重ね 良い習慣を身につけ、心地よく生きていきましょう。 水野さと美 シュクレ メディシナルハーブ主宰...