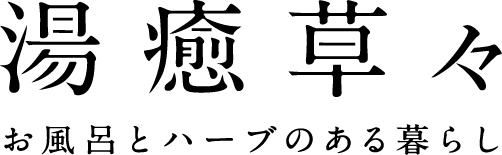読みもの

土用の丑の日には桃の葉を入れた「丑湯」で無病息災を願う
7月17日に気象台より東海地方の梅雨明けが発表され、過去最長62日間の長い梅雨であったことが話題になりました。 これから本格的に蒸し暑~い夏が始まるわけですが、猛暑で食欲が落ちるとどうしても冷たい食べ物や飲み物が続いてしまいがち。ちょうど夏バテが心配になってくるそんな頃にやってくるのが「土用の丑の日」です。 土用の丑の日といえば鰻(うなぎ)を食べるのが一般的ですが、薬草をお湯に入れて入浴をする「丑湯(うしゆ)」という習慣もあります。 ハーブ湯としてのメリットや丑湯の入り方などについて、ご紹介したいと思います。 そもそも土用の丑とは? 毎年この時期になるとスーパーやコンビニなどで「土用の丑の日には鰻を食べよう!」というポスターが並び、全国の小学生たちは「なんで土用の丑の日なのに土曜日じゃないんだろう?」と頭を悩ませるわけですが、「土用の丑の日」とはどういったものなのでしょうか? 簡単に言うと、「土用」という期間のうち「丑の日」である日のことを「土用の丑の日」と言い、梅雨明け頃になる「夏の土用の丑の日」が一般的に有名である、という説明になります。 「土用」っていつのこと? 「土用」とは「土旺用事(どおうようじ)」の略で、二十四節気のうちの四立と言われる「立春」「立夏」「立秋」「立冬」前の約18日間(または約19日間)のことをいいます。各季節の変わり目にあるということです。 2021年の土用 冬土用(立春前):1月17日(日)~2月2日(火) 春土用(立夏前):4月17日(土)~5月4日(火) 夏土用(立秋前):7月19日(月)~8月6日(金) 秋土用(立冬前):10月20日(水)~11月6日(土) 一般的には立秋前の夏の土用が最も有名ですが、実は1年に4回もあったというのは、知らない人も多いのではないでしょうか。 「丑の日」っていつのこと? 丑の日は十二支(子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)の2番目にくる「丑(うし)」のことです。 十二支は年を数えるときに使われるのが一般的ですが、 実は方角や月、日にちを数えるのにも使われます。つまり、約18日間の土用の期間のうち、 12日周期で割り当てられている十二支が「丑の日」にあたる日のことを「土用の丑の日」と呼びますので、1日だけでなく2日存在することもあります。その場合は1日目を「一の丑」、2日目を「二の丑」と呼びます。 2021年土用の丑の日 冬土用(立春前):1月17日(日)、29(金) 春土用(立夏前):4月23日(金) 夏土用(立秋前):7月28日(水) 秋土用(立冬前):10月20日(水)、11月1日(月) このように春夏秋冬すべてに「土用の丑の日」があります。 桃の葉を入れた「丑湯」で夏バテ防止、無病息災を願う 土用の丑の日には鰻を食べるほか、薬草をお湯に入れて入浴する「丑湯」という習慣があります。 現代日本では、入浴剤を入れてお風呂に浸かることはいつでも気軽にできることになっていますが、今よりもお湯が大変貴重で、毎日お風呂にお湯を溜めることができなかった時代には、蒸し暑い夏に入る薬草風呂は格別に爽やかなことだったようです。 夏バテ防止や疲労回復のために入る「丑湯」には無病息災を願う意味もあり、江戸時代にはとくに桃の葉を入れた桃湯を丑湯としていたそうです。 ...

緑と風とハーブに癒される時間 / 三重県多気町・本草研究所RINNE(VISON)
こちらのコラムでは、自分らしくナチュラルに暮らすためのポイントを、各務原の街の魅力と共にお伝えしています。 いつもは岐阜県各務原市の街の魅力を中心にお伝えしているこちらのコラムですが、前回に続き今回は少し遠出して三重県まで。 各務原市から三重県多気町まで、高速道路を使って車で約2時間。 新しくできた体験型の観光スポット「VISON」の中にある、本草研究所RINNEさんにお邪魔してきました。 本草研究所RINNE 三重県多気郡多気町ヴィソン672番1 本草研究所2OPEN 10:00-18:00https://www.instagram.com/yakusou.rinne_vison/ VISON 三重県多気郡多気町ヴィソン672番1(店舗により営業時間などは異なります)https://vison.jp/ 三重県多気町に広大なエリアを開拓して作られた体験型の観光スポット「VISON」は、食・文化・アートとテクノロジーが集結する地方創生プロジェクトとしてスタートしました。 様々な飲食物販のショップエリア「マルシェヴィソン」や、温浴施設「本草湯」などが既にオープンしていますが、2021年7月20日には宿泊施設「ホテルヴィソン」をはじめ、素敵なお店が一斉にオープン予定です。 さらにその後も、ミュージアムや農園なども加わり、一大観光エリアとなるでしょう。 すごいですよね。 この日は時間が取れずVISON全てを見ることができなかったのですが、個人的にも仲良くしていただいている本草研究所RINNEさんでお茶をしながら、ゆっくりと過ごさせていただきました。 本草研究所RINNEさんは、VISONのエリア内でも山の中腹に位置するショップ。 素晴らしいロケーションで、ここまで来るくるだけで一気にリゾートのような気分になります。 国産のハーブを使った「和草茶」を中心とした、ハーブや身体に心地よいグッズなどをの販売をするショップに、ハーブティやヴィーガンスイーツを中心としたカフェが併設されている素敵な場所です。 開放感のあるガラス張りの店内からは、山の稜線が見えます。 夕暮れ時には山に沈んでいく美しい夕日が見れるようで、スタッフさんたちも「毎日心地よい環境で過ごせることが嬉しい」とおっしゃっていたのが印象的でした。 甘さを控えたハーブドリンクは、赤丸薄荷とハイビスカスのティーソーダ。 すっきりとした後味で、いつまでも飲んでいられるような爽やかさがあります。 季節によっても採れるハーブはどんどん変わっていきます。 行くたびに新しいハーブティーやドリンクに出会えるというのも魅力的ですよね。 焼き菓子ももちろん、RINNEさんのオリジナル。 ハーブドリンクとの相性を考えられたお菓子は、素材そのものの味わいがとてもしっかりしています。 スパイスや小麦だけでなく、みりんや塩麹、ほうろく菜種油など調味料にもこだわり、素朴ながらも繊細で奥行きのある味わい。 口に入れるたびにハッとするような新鮮さがあります。 ショップでは、オリジナルの和草茶や焼き菓子をなどの美味しいものをはじめ、菊花せんこうなど植物を使った日用品、自然由来成分100%の化粧品など身体に使うものまで、様々なラインナップで楽しめます。...

スパイスの力で医食同源 アーユルヴェーダ料理を作ってみよう
インドの留学生とオンラインカレー教室をしたり、最近はスリランカ出身の方にインド地方の食文化について学んでいる、フードビジネスコンサルタントのひらつかです。 前回は、ジンジャーチャイのお話をさせていただきました。https://yuyu-sousou.com/blogs/column/20210108 今回は、医食同源の国とも言われているインド地方のアーユルヴェーダの教えからなるスパイス料理についてのお話です。 インドの伝統医学 インドでは伝統医学という医学の分野が存在しており、約5000年前から存在しています。体質に合わせて病気になりにくい体をつくるいわば「予防医学」の考え方です。病気になってから治すのではなく、病気にならない身体づくりや生活習慣の教えが古典には記載があります。アーユルヴェーダは、生き方の指針ともいえ、自分らしく、幸せに生きることを目指す、人間本来の礎ともいえるシンプルなテーマともいえます。 また、アーユルヴェーダでは、人の体や心、生きようとするエネルギーは食べ物によって作られるとされ、それぞれの体質や症状にあった食事は、薬よりも大切であるとされています。 スパイスの役割 アーユルヴェーダの影響を多く受けるインド地方において、スパイスやハーブは、なくてはならないものです。主にスパイスの役割は、香り付けと辛み、色付けです。スパイスで味を付けるという役割はなく、風味で嗜好性を高め料理にアクセントを与えます。スパイスのもう一つの役割として、食欲増進や消化代謝を促すとされ、体の調子を整える薬としての役割もあります。 インド地方での食事のスタイルは、一枚の皿のうえに主食(ご飯やナン、チャパティ)、副菜やアチャールと呼ばれれる漬物のような付け合わせも一緒に盛り付け、それらを少しずつ混ぜながら食べます。一度の食事でも組み合わせによって味に変化が付けられるために飽きることなく食べられます。 今回は、わたしの友人でもありインド系の食文化について教えてもらっている、スリランカ出身のリリさんに日本でも手に入りやすい材料を使って、スパイスを使った料理を紹介します。 かぼちゃのカレー かぼちゃ 500g A 塩 小3/4 カレーパウダー 小1/2 玄米 3/4 ココナッツファイン 25gココナッツミルク 200ml B 玉ねぎ(薄切り)1/2個 にんにく(みじん切り)1片 青唐辛子1本 粉唐辛子小1/2 こしょう少々 1.かぼちゃを一口大に切り、Aをまぶしておく2.玄米とココナッツファインをフライパンで乾煎りしたあと、 ココナッツミルクと一緒にミキサーにかけペーストにする。3.1とB、水400mlを入れて中火で、かぼちゃが柔らかくなるまで煮る...

夏の紫外線ストレスやシワ予防に!! 免疫増強に!! 夏のHSP入浴法でセルフケアを
ヒートショックプロテイン(HSP)の入浴法を公に広めたいと研究している、HSPプロジェクト研究所所長 医学博士 伊藤要子です。活動を初めてからはや20年近くなりました。この間に、夏の外気温は明らかに高くなりました。また、夏と冬の外気温の温度差は30℃近くあり、HSP入浴法を夏・冬同じようには実施できません。そこで、現在の気温を考慮して、夏バージョンのHSP入浴法をわかりやすく、すぐに実践できるよう解説していますので是非、試してみてください。 夏も必要なHSP 夏は、シャワーで済ませがちになりますが、お肌のためにも、夏の暑さに耐えうる体づくりのためにも、週2回のHSP入浴法をおすすめします。HSPには、ストレス防御作用があります、特に夏の強力な紫外線ストレスに対しては、体の中から紫外線ストレスを予防してシミ、シワ予防に役立ちます。 HSPは、各種病原体による感染ストレスに対して免疫を増強させる作用もあり、ウイルスや細菌など様々な感染に対する免疫増強作用があります。 暑い夏に、 “なぜHSP入浴法を?” 「夏の暑さで十分ではないか」と考える方もいるかと思いますが、夏の気候(外気温35℃以上が続く暑さ)による暑さと、HSP入浴法(40~42℃での10~20分の加温と10~15分の保温)のメリハリのある加温とは、身体に与える影響が違います。HSP入浴法では、所定の温度で所定の時間、加温することで身体に熱ストレスを与え、HSPを増加させることができます。 それでは、さっそく夏バージョンHSP入浴法にトライしてみましょう。 準備するもの ① 飲料水 夏は脱水になりやすいため必ず飲料水を準備しましょう。 HSP入浴法で出る汗は、体温調節のための汗なので、成分はほとんどが水分ですので、普通の水やお茶でかまいません のぼせやすい人、汗が出にくい人*は入浴前にも水分をとっておきましょう。 入浴中、保温中でも水分が欲しくなったら、水分補給して構いません。 冷たい飲料水は体温を下げ、体を冷やすので避けましょう**。 飲料水の準備での参考項目 *のぼせやすい人は、身体の熱が十分に汗となって排泄できないことが原因の1つです。汗がでやすいように、前もって水分をとっておきましょう。 *汗が出にくい人は、身体の熱がうまく体外に捨てられず、熱中症にもなりやすいです。外気温が30℃を超すようになれば、身体の熱を捨てる手段は汗しかありません。よって、汗を大量に出すHSP入浴法は、汗がなかなかでない人の発汗の練習にもなります。 **冷たい飲料水を飲むと、それが体温になるまで熱を身体から奪うので、体温が下がってしまいます。保温終了後なら冷たい飲料水でもOKですので、保温の終了まで少し我慢しましょう。常温の飲料水ならいつでもOKです。 ② 防水タイプの舌下型体温計 最初のうちは、防水タイプの舌下型体温計で体温を確認するとよいでしょう。慣れてきたら、自分の感覚で何度くらいか分かるようになります。 ③ 防水温湿時計(時計と温度計(室温)や湿度計も一緒についているのが便利) 入浴時間を測るために防水温湿度計を用意しましょう。また、タイマーを付けて、入浴時間を確認するのも良いでしょう。浴室内の温度や湿度機能がついた時計だと便利です。 ④ 湯温計 実際の湯船の湯温を確認するのに便利です。お風呂に取り付けられた湯温設定は、浴槽に流れ込む湯の温度で、浴槽に溜まった湯の温度ではありません。実際の湯の温度は、一般に、設定した温度より若干低くなります。 ⑤ バスタオルや着替え バスタオルや着替えは、水のかからない浴室の隅か、脱衣所の手の届く所に準備しておきましょう。 ⑥ お楽しみグッズ 入浴中、じっと動かずに湯船に浸かっていると、入浴時間がとても長く感じます。 私のサイトに掲載された「運動するHSP入浴法」に記載された簡単な運動をするのも良いでしょう。https://www.youko-itoh-hsp.com/hsp/hsp-bath-sports/体温も上がりやすく、時間が経つのが早いです。...

和ハーブインストラクター半谷美野子さんに学ぶ 「和ハーブを身近に感じる」
和ハーブとは、どのような植物があると思いますか。ヨモギやドクダミ、シソ、ユズ、サンショウ、ショウガなど、日本に古くからある、日本人が自然と暮らしに取り入れてきた植物たちのことです。一般社団法人 和ハーブ協会では、「在来種(日本原産)、あるいは江戸時代以前より日本に広く自生している有用植物」と定義されています。 そんな植物たちも、育つ環境はそれぞれ。自分たちの好きな場所を見つけて自生し、そこかしこに存在します。 今回は、身近にある和ハーブの活用法を和ハーブインストラクター半谷美野子さんお聞きしました。 日本ハッカ 日陰が好きなハーブ。西洋ミント(ペパーミントやスペアミント)は日が当たる場所でも大丈夫ですが、日本ハッカは暑い夏が苦手です。西洋ミントよりも深く甘い香りが特徴の日本ハッカは、フレッシュでもドライでも、ハーブティーにするとすっきり美味しくいただけます。食べ過ぎたり、お腹が重いときにもオススメです。 また、抗菌作用も持っているのでティーでうがいをしても良いですね。お風呂に入れて使用すれば、さわやかな香りに癒されます。 ジュズダマ 湿っているところが大好きなジュズダマは、ハトムギの野生種です。ネックレスやブレスレット作りに使ったことのある方もいらっしゃると思います。 使用するのは果実の部分。最初は緑色ですが、徐々に艶のある灰色や黒、ベージュ色になります。(画像参照)灰色になったジュズダマの果実を天日に干して乾燥させると、お茶として利用することができますが、ハトムギより果実が硬いため、果皮を割る作業が大変だそうです。 ツワブキ 半日陰が好きな野草。秋に黄色の花を咲かせます。観葉植物として販売もされていますが、葉茎を食用としても使用できます。 茎はふきのように食べることができるそうです。アクが強いのでアク抜きは必須です。やけどをした際に、生葉を炙り、患部に貼ったり、おむつかぶれに貼る人もいるそうです。 ヤブカンゾウ 7月~8月にオレンジの花を咲かせます。つぼみはアクも少なくサッと茹でると、シャキシャキとして甘みがあるので、ついつい食べ過ぎることも。 ただし、ヤブカンゾウには利尿作用や緩下作用があるため、食べ過ぎるとおなかが緩くなることもあるそうです。ご注意を。一度に食べる量は、つぼみ5~6個程度までにしたほうが無難です。 また、葉や新芽も茹でて食べることができます。中国では、花を乾燥させたものを「キンシンサイ」と呼び、高級中華料理に使用されているそうです。 アカメガシワ 日当たりのよいところに最初に出てくる、パイオニアと呼ばれる植物。ポリフェノールが豊富で、樹皮を乾燥させたものを煎じて飲むと胃腸に良いそう。 ただし、薬学博士の故村上先生よると、アカメガシワはストレスによって起こる各種疾患には効果がないと述べています。そして、入浴の際に塩と一緒に使用すると香りはないが肌にもよく、身体も軽くなるそうです。(薬草を食べる アカメガシワ 著書 村上光太郎) また、アカメガシワには蜜腺があり、アリが蜜によって来ることで、ほかの虫を寄せ付けないという生存戦略をもっています。新芽の赤い毛をこすると緑色になりますが、赤い毛は若い葉を紫外線や他の虫から自身を守るためだそうで、大きくなると赤くなくなります。 *一説では虫たちは、赤い葉=枯れていると思うといわれています。 ...

仏生山の旅 ~後編/ 植物編~
仏生山の森をたずねて 香川県高松市の中心に位置する、古いものと新しい物が心地良く交わる町「仏生山(ぶっしょうざん)」。その仏生山で近年街にも県外からの観光者にも愛される温泉について、前回はご紹介いたしました。前編はこちらhttps://yuyu-sousou.com/blogs/column/20210521_kagawa_onsen ゆったりとした時間の流れる、現代的でお洒落な館内。とろりとした湯ざわりの肌に優しいお風呂は、どこからでも丁寧に整備された中庭を眺められ、ついつい長湯をしてしまいます。 今日のお話しは、そんな仏生山温泉から車で約5分。静かな門前町からちょっと外れた、のどかな田舎の風景の真ん中にできた新しい場所。 最近四国の友達のSNSでよく見かける場所、カフェなのか、植物園なのか、動物もいる…?「仏生山の森」のご紹介です。「仏生山の森」は"仏生山の街に根付く"ことをテーマとした自然や食事の体験が出来る場…簡単に言うとレストランとカフェとBBQテラスとケーキ屋さんと料理教室と植物園の楽しめる小さな複合施設です。 『「仏生山の森」の中には、さまざまな憩いの場があります。そして、そこに完成形はありません自然のままに、移りゆく季節と人々の暮らしに合わせながら、心地よく変化していきます。』HPより(https://busshozan-no-mori.com/) 香川県産の野菜やお肉を使った料理、お砂糖などの素材にこだわったスイーツ、それらを訪れた仲間たちと楽しめるBBQ…SNS上では食事の充実さに注目がいきますが、私が感動したのは「仏生山の森ガーデン」です。「100年続く自然」をテーマにした静かなお庭。ガーデニングでは珍しい、造園に使われている植物の95%が宿根草、多年草を用いているそうです。 偶然この広いガーデンを作り上げた高橋彌生(たかはしやよい)さんにお会いすることができ、お話を聞くことができました。 「3000株もの植物を植え、それぞれがそれぞれの適した季節に、最適な状態で観られるようにするのはとても大変なこと。 毎日のお手入れとしっかりした知識、あとは様子を見て理解できる目。植物は可愛いでしょう。それぞれ得意な時期と場所があって、それを知ってあげて、良い時に良く見えるように生かしてあげないと!」 まるで子どもの成長を楽しむように語る高橋さん。19歳の時から植物について学び、50歳から本格的なガーデナーになられた、半世紀も人と同様に植物に愛情を向けてきた方です。 「仏生山の森」全体のテーマである「街に根付く」事と、昨今の庭つくりの流行である宿根草に共通点を得て、「100年先も変化しながら強く美しく街に愛される庭にしていこう。」と3年前に始まったガーデン作り。 3年目にしてようやく最初に植えたものから根が広がり、強く良い状態で咲くようになってきてくれたそうです。 暖かい香川県といえどもまだ3月の寒い時に訪れたので、周りの畑には菜の花が咲き誇っていましたが、青々とした芝生や新緑には遠い頃。にもかかわらず、ガーデンには多種多様の美しい緑や花が咲き誇っていました。 寒い時には背が低くて葉の強い植物が、暖かくなってくると大きな花をつけるものが目立ちだし華やかに。夏には背の高いグラスが風になびいて美しく、秋には木々の紅葉のように足元の葉も色づき、冬を越すための剪定や手入れを入念にすることで、また季節が巡っていく。 そうして年々、強く広くそれぞれが根を広げ、最適な場所を自分たちで選び育っていく。 物言わぬ植物達の意思を感じ取りながら、成長の手助けをする。「とっても大変だけど楽しいのよ。」とお話ししていただきました。 ホームページに記載されているこの言葉とガーデンは欠如していた自然のままにいきる感覚を思い出させてくれた気がしました。 それは日々のうつろいや変化を恐れず、そのままの美しさを認める事。何かをこうしなければ、自分はこうでなければ…無意識のうちにありもしない完成形を求め、自分を縛り、窮屈な思いをしている事。 肩に力が入り、躍起になって理想や完成形を追い求める事は、人が生きる上で大切な事で、その力があるからこそ、人間はここまでの発展をしてこられた事は間違いありません。 しかし、本来人も自然の一部。生まれそして死んでいくただの生命の一つでしかありません。「未完成でいい。」植物を通してこの言葉が思い出させてくれる原始的な生き物としての人の姿。 ありのままを認め、花が咲かない時も、目に見えない土の中で根が眠っている期間も含めて愛する。感じるままに、肩の力を抜いて、生き物としての自分は何を求めているか。 ただ花や緑に癒されるだけでは終わらない、自分自身に問いかけ、気づきを得た旅でした。それにしても、本当に美しいお庭でした。ローズマリーって、日当たりと土の質があっていたらゴロゴロとした岩の間でも根を張って育つそうです。 育ちすぎて邪魔者扱いされがちなミントがあちこちでツヤツヤとした緑のアクセントになり、グランドカバーの多くがタイムの仲間だったり、見知ったハーブが見知らぬ姿でイキイキと育っていました。 私の働く恵みの湯にもハーブ園があります。 主に入浴剤やサウナのロウリュウに使用するために収穫を目的として整地し栽培しています。 整然と整えられた中でも、自分達で場所を選ぶように年々移動するカモミールや、去年はいなかった虫の発生など、植物は思った通りにいかないなと日々考えさせられます。 暑い日が増えてきて、最も植物が元気に育つ時期がきました。 頭を働かせるばかりの日常から少しだけ離れ、自然や植物に触れられる畑の時間。 植物の声に耳を傾け、未完成の生む変化を楽しみながら成長を見守っていきたいと思います。 参考:仏生山の森 公式サイト https://busshozan-no-mori.com/...