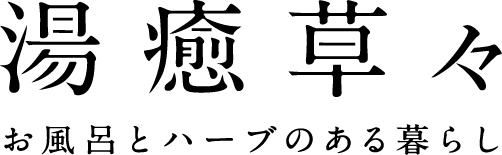読みもの

まちといる人 自分にも地球にもストレスのない暮らし
秋風が冷たく感じられる季節になり、過ごしやすさや心地よさを感じられるようになってきました。 気温が低下していくと、なぜかもの悲しくなったりどうしても調子が上がらない日が出たり…気力の低下と共に、知らず知らずのうちにふえているのがストレスです。 根本的な解決方法があるならほしい。どうすればストレス少なく生きられるのだろうと、涼しくなってくると苦しくなってくるのは私だけでしょうか… ストレスは生活の中で生まれてくるものですが、解決策として挙げられるものは「睡眠」「お風呂」「一人の時間」など日常をちょっとアレンジするものが中心です。 しかし、根本になる原因を取り除かない事には、その場凌ぎの解消法にしかならないず、ストレスの緩和、解消の意味を見出せない気持ちもあります。 そんなことを漠然と考える日々の中、一人の魅力的な女性に出会いました。しなやかで穏やか、常に身体のどこからもストレスを感じない自然体でありながらはっきりとした芯を感じる人、妙子セニガリエズィ(以下タエさん)さんのご紹介です。 前回私の書かせていただいたコラム「まちといる人《未来、人間、自然=デザイン》ライフスタイルデザイナー アレさんに聞く」ではライフスタイルデザイナーのアレさんに、日々の生活をランクアップさせるデザインの考え方についてお聞きしました。 https://yuyu-sousou.com/blogs/gifu-kakamigahara/20210716_lifedesign タエさんはアレさんの奥様で、岐阜県各務原市で自然に囲まれたおうちで生活しています。 タエさんとアレさんの出会いはオーストラリア。10年ほど前にそれぞれワーキングホリデーで同じホステルに滞在していたのがきっかけです。その後行動を共にし、生活するうちに、アレさんは民族文化や工芸品や職人技術に心を惹かれて、タエさんはそれまでもご自身がお仕事として行っていたマッサージの新しい技術を深めて行きました。 技術や知識として新しいものを吸収していく一方で、多国籍の人のあつまるホステルや、ホームステイ先での生活で、タエさんはふと違和感を覚えたそうです。 大きなきっかけはホームステイ先のシャワールーム。いつも通りシャワーを浴びて髪や体を洗って流す、日本では当然の習慣、なんならお湯も張りたいな、そんなお風呂習慣を行うと、ファミリーから「日本人は綺麗好きでお風呂が長い」という指摘が出たそうです。聞けば、そのエリアは雨が少なくタンクに貯まったお水がなくなったら終了。お風呂は最小限で、よっぽど暑くて汗をかかないと髪も毎日は洗わないそうです。 「えっ?シャワーだけなのに?」と思うと同時にタエさんが気づいたのは、いかに自分がそもそもの習慣に疑問を持たずにいたかということです。なんとなくいつもしてるから、と考えたり選択した自覚もなく、日々生活していることにちょっとした恐怖心に近いものも感じたそうです。 小さなきっかけですが、タエさんにはあらゆることに通じる大きな出来事でした。それ以来、日々のあらゆる選択を意識するようになったそうです。 朝起きて、身支度をし、食事を取り、仕事をし、買い物をして、お風呂に入り、眠る。 何気なくすぎていく日常の中に、どれほど多くの【選択】がひそんでいて、自分達はそれを【習慣】として流してしまっているかに気付く。そして、日常の中でストレスや不満が生まれてくるのは、この習慣化した選択の影響があり、一つ一つを見直すことで生活をもっといいものに変化させていけるのではないかと思ったそうです。 それから、タエさんは生活の中で【習慣】になっていることに直面すると「これは”今”の自分に必要か」と自分に問いかけるようになりました。 その結果、身の回りから必要ないものが減り、ゴミが減り、どんどん身軽になって、ストレス自体が消えていく感覚を得ていきました。 さらには、これまで以上に環境や気候にも目を向け流ようになり、自分にとっての心地良い暮らしのための選択が、地球環境にも良い影響を与えていけるのではと感じ始めました。 住む場所が点々と変わる生活がおわり、アレさんとともに日本に帰国し、家族となって一つのところに暮らすようになり、これまで以上に「長く物を使うこと」「ゴミや無駄なものを少なく生活すること」が重要になってきました。 タエさん達には新しい【日常の習慣】になったものの中で、私からしたら驚きで魅力的な生活のテクニックを紹介します。 まずは【蜜蝋ラップ】。古いハンカチや手ぬぐいに蜜蝋を塗ったものです。野菜や食品に触れても安心な素材で、優しく鮮度を保ってくれます。 使用後は水で洗い冷蔵庫で保管すると半年〜1年使えて、プラスチックゴミの現象に大きく貢献してくれます。 なんとなく知っていたけれど実際見せてもらうとまず可愛い!カラフルでくったりした質感が見るだけでうれしくなります。 ラップとしてお皿や野菜を包むだけでなく、公園などにいくときに持っていくと、折りたたんでお皿代わりに、しっかり漏れがないようにするとコップ代わりにもなるそうです。 「そもそもお気に入りだった古いハンカチやハギレを使用すると、大切なものを手放す悲しみがないし、お気に入りがいつまでも手元にあるのが嬉しくなる」とタエさんは言います。 次に広大なお庭に設置された【コンポスト】。タエさんの手作りで家族には「ヒッポくん」と呼ばれてペットのように可愛がられています。料理の際に出る生ゴミをヒッポくんに入れてこもった熱と微生物の働きで肥やしへと変わり、畑の土の栄養になって土に却って行きます。 タエさんと食事をした際に、料理をするところを見せていただくと、生ゴミがほとんどでないことに驚きます。過食部は無駄なく使い、わずかに出るゴミは土に返す。...

目の疲れにぴったり!和ハーブ香るアイピロー
みなさん、目はお疲れではありませんか? 気づけばスマホを見ていたり、パソコンで調べもの、おうち時間が増えて動画ばかり見てしまったり・・・、と仕事以外でも目を酷使してしまっている方も多いのではないでしょうか。 かくいう私も目の使い過ぎで目がシバシバしたり、肩や首がこったり、目の上が重くなってくることも・・・。そんな時に大活躍なのが、アイピローです。 アイピローとは? アイピローとは直訳すると、“目の枕”ですが、目の上にのせて、適度な重みと温めたり冷やしたりすることで、目をリラックスさせるものが一般的に“アイピロー”と呼ばれています。また安眠を目的とするものはアイマスクと呼びわけているようです。 アイピローにおすすめの和ハーブ ・ヨモギ(蓬):キク科(キク科アレルギーの方は注意!) 浸かってよし、塗ってよし、嗅いでよし、燃やしてよしの万能和ハーブ。血行、新陳代謝の促進や、抗菌の作用もあると言われ、活用用途は色々。アイピローに入れれば、目のヨモギ蒸しになります。 ・ゲットウ(月桃):ショウガ科 スーッとした香りの中に甘さのある香り。沖縄ではお餅を包んだり、民芸品を作ったりと古くから活用されています。緊張した筋肉を緩める作用もあると言われ、今大注目の和ハーブ。 ・クロモジ(黒文字):クスノキ科 清涼感のある香りは心を落ち着かせてくれます。お茶にしても、入浴剤にしてもいい香りで大人気。心にも身体もリラックスさせてくれます。 ・カキドオシ(垣通):シソ科 ハーブらしい爽やかな香りで、食べても美味しく、昔から健康茶として飲まれてきた和ハーブ。入浴剤として使うと、体や心の疲れを癒してくれるそうです。 アイピローは、色々売られていますが、お家にあるものや100円ショップで購入できるもので、簡単に作ることができます。今回は和ハーブやハーブの香りを楽しめる、アイピローをご紹介したいと思います。 アイピローの作り方 【アイピローの材料】 ・内袋用のお茶パック(小)2枚 (自分で小さい布袋で縫ってもよい)・玄米、ケツメイシ(エビスグサの種=ハブ茶の原料)、アズキなど 100~150g・自分の好きな香りのハーブ 適量・ドライ和ハーブ:ヨモギ、クロモジ、月桃、カキドオシなどがおすすめ。・ドライハーブ:ラベンダーやカモミール・ジャーマンなど・ハンカチタオル 1枚 20㎝×20㎝ (新品でも使っているものでもOK) ・スナップボタン 1~2個 ・裁縫道具(必要であればミシン) ケツメイシ(エビスグサの種) (左上)ゲットウ(右上)ラベンダー(左下)カモミール(右下)ヨモギ アイピローの作り方 1.ハンカチタオルを表面が見えるように、半分に折る。2.短い一辺を残して、開いている2辺をチクチク縫う。 3.縫わなかった、開いている辺にスナップをつける。...

伊吹山の麓だからできた無農薬の在来茶 傳六茶園 森さんに会いに行く
「天空の古来茶」(※1)の煎茶を飲んだとき、その喉越しに驚きました。 きれいな若草色をしたお茶は、緑茶の苦味がしっかり感じられるのにお水のようにさらさらと喉を通ります。 鼻から抜ける香りはどこか懐かしくて、こんなに後味がスッキリとしたお茶は今までに飲んだことがありませんでした。 どんな人がこのお茶を作っているのだろう?春日地区ってどんなところだろうと気になったので、茶農家の「傳六茶園」の森さんに会いに、伊吹山の麓まで行ってきました。 傳六茶園さんは岐阜県揖斐郡揖斐川町の春日地区に位置する「春日の小さな茶農家」さんです。 (※1)伊吹山の麓、揖斐郡揖斐川町の春日地区で栽培されている無農薬栽培された在来品種名。平成22年からはブランド名を「天空の古来茶」とし、茶生産・販売。 小雨の降る中の訪問にも関わらず、代表の森さんが快くお出迎えをしてくださいました。 ご挨拶もそこそこに、同行した息子たちが退屈しないようにと周辺や敷地内をどんどん案内してくれる森さん。「ここにサワガニがいるんだよ」という、興味をそそるパワーワードのおかげで、緊張気味の子どもたちの顔があっという間に笑顔になりました。 お部屋に案内いただくと、さっそく2種類の「天空の古来茶」を淹れてもらいました。 「うん、おいしい。そうそう、この口当たり」 「煎茶」はストレートに緑茶の苦味を感じることができますが、喉を通ると何も引っかかることなくすーっと体に染み渡ります。 「一番摘みほうじ茶」は澄んだ飴色のほんのりとした甘み、優しい口当たり、豊かな香りが鼻に抜け、どこか懐かしさを覚える味。 一口いただくごとに呼吸が整い、肩の力が自然と抜けていきます。 今回は、特別にお茶と一緒にいろいろな茶器ともにお茶菓子までいただきました。その器の種類の多さや気遣いに、日頃からお茶の時間を大切にされているのかと伺えば、「そんなことないよ」と森さんは言います。美味しいお菓子を頂いたときは器やお皿にこだわって落ち着いた時間を過ごしたいけれど、普段はゴクゴクと飲んで喉を潤しているそう。 「ウチのお茶(天空の古来茶)を飲む人には茶葉の量やお湯の温度を気にするよりも、その人が美味しいと思う淹れ方で飲んでもらえればそれで良い。そう飲んでもらえるのが嬉しい」と。 その気取らない言葉に、失礼ながらも私となんら変わらない飲み方をするのだなと思いました。 日本茶は、今から1200年以上も前に最澄が唐より持ち帰ったものが始まりと言われています。現在、日本で流通しているお茶のほとんどが、機械による摘み取りや加工がしやすい「やぶきた茶」というものです。 しかし、春日の地域一帯では山深い地形が災いし、1200年以上前に唐から伝来したままの在来茶を生産し守り続けています。摘み取り、製茶加工されたお茶は、農薬や肥料を使用していないために余計なものが一切混ざらず、お茶本来の味が抽出されます。おばあちゃんのお家を思い出すような、昔ながらの豊かな味わいです。 では、なぜ春日では在来茶の無農薬栽培を700年以上もの長い間守り続けて来られたのでしょう。農薬を使用しないことがこだわりなのかと聞けば、使用しないのではなくて、必要がないそうです。 山間部に位置する春日は冷涼で朝霧が発生しやすく日照時間も限られています。そこで育ったお茶の新芽は、柔らかく、瑞々しく、明るい黄緑色をしています。 平地なら暖かくなるにつれて虫の被害に悩まされてしまうので農薬を使わざるを得ませんが、ここ春日は標高が高いため刈り入れの時期に虫が付きにくいのだそう。 また、春日の人々は昔から家庭で飲むためにお茶を栽培してきたと言います。 他所に売るでもなく、赤ちゃんからお年寄りまで家族みんなに美味しいお茶を飲んでもらいたい。害虫被害がないから農薬も必要ない。 農薬の入ったお茶を家族に飲ませたくない。森さんの答えは、とてもシンプルでした。 日当たりや雪解け水など、人間が手を加えることができない春日の自然が生み出したお茶。 手間暇はかけるが、余計なことはしない。 ありのままのお茶を守る、その心がこだわりのようです。 決して敷居の高い特別なお茶をつくりたいわけではありません。 代々、守られてきた生産量の少ない無農薬の在来茶を、春日のお茶農家の生活を守るためにブランド化したのが「天空の古来茶」です。...

お料理にハーブのアクセントを。美味しく元気に夏を乗り越えよう!
こちらのコラムでは、自分らしくナチュラルに暮らすためのポイントを、各務原の街の魅力と共にお伝えしています。 ハーブが生き生きとする夏。 自宅の庭で育てていたり、畑のある実家やご近所さんから頂いたり、この時期は夏野菜やハーブが手に入りやすいですよね。 いつもの夏野菜もハーブの力で風味良く、ちょっとおしゃれに。 お料理の専門家ではない私でも、ちょっとの工夫で楽しめる「おうちごはん」を紹介します。 まずは庭でたっぷり採れた大葉です。 フレッシュな状態であれば、いつものお料理に刻んでかけるだけでとっても風味が良くなり爽やかに。 揚げたナスをめんつゆにつけて冷やして味を染み込ませた「ナスの揚げ浸し」にかけたり、ズッキーニを薄切りにして梅ダレを加えた和え物にかけたり……。 もちろん、素麵などの薬味にもいいですよね。 水気をしっかり取ってから千切りにして冷凍しておくと、長い間楽しめます。凍ったまま炒め物に入れたり、汁物に入れてもいいですね。 大葉がたくさんあったので、大葉のジェノベーゼソースを作ってみました。 水気を拭いた大葉、炒ったくるみ、ニンニク、粉チーズ、塩、オリーブオイルをフードプロセッサーでペーストにするだけ。 実はとても簡単なのでたくさんの大葉が手に入ったらぜひやってみてください。 ジップ式の袋に薄く伸ばして入れて冷凍すれば、必要な分だけ割って解凍して使えます。 バジルのジェノベーゼと同様に、茹でたジャガイモやパスタと絡めて食べたり、茹でたタコやトマトにかけてカルパッチョにしたりなど、色々使えますよ。 今回は軽く湯がいたオクラとトマトをトッピングしてみました。 次はバジルです。バジルはやっぱりトマトとの相性が抜群ですよね。 ミニトマトやスライストマトにバジルをたっぷり盛って、塩、粒胡椒、酢、オリーブオイルをかけるだけで夏らしいサラダが完成です。 もしたくさんあれば、大葉と同じくジェノベーゼソースにするのもおすすめです。 独特な香りがクセになる、セロリもこの季節のお料理のポイントになるハーブですね。 葉の部分はベーコンやお肉と炒めたり、スープに入れたり、軽く茹でてお浸しにしても美味しいです。 茎の部分は短くカットしてピクルスに。 白ワイン、水、酢、砂糖、塩、ホールペッパー、ローリエ、鷹の爪をひと煮立ちさせたピクルス液を、煮沸した容器に入れたセロリにひたひたに入れて冷蔵庫へ。 シャキシャキさっぱりとしたセロリは、カレーやグリルチキンなどの付け合わせにしてもいいですね。 夏野菜のワンプレートにするのはいかがでしょう。...

「無理をしない」私のサウナ生活
今、大人気のサウナ。以前は、男性の利用が多かったのですが、最近では女性の利用も増えています。#サウナー女子 というハッシュタグも多いですよね。 ラトビアでの衝撃サウナ体験 私がサウナを始めるきっかけとなったのは3年ほど前、バルト三国へハーブの旅に出かけた時、ラトビアで体験したラトビア式サウナ「ピルツ」です。 ピルツは、フィンランド式サウナにも似ていますが、ここで初めてハーブサウナを体験しました。 それはとても衝撃的でした。 最初は我慢のできる温度で、これなら大丈夫と安心していたのですが(これは、ただのウォームアップでした)サウナ師さんがサウナストーンに大量の水をかけ始めると、室内はたちまち高温状態へ。 仰向けになり寝ている私に、サウナ師さんが白樺や菩提樹など4種ほどのハーブ束を熱波とともに何度も身体に押しあてます。 サウナ室は常に高温の蒸気が充満し、まだサウナに慣れていなかった私は、とにかく熱さに耐えるしかありませんでした。15分ほどの時間でしたが、苦しいほどの蒸気と熱波に気を失いそうになるほどでした。 その後のクールダウンでは、天にも昇るような気分になり、いわゆる「ととのう」という感覚を初めて経験したのもこの時でした。その時は、まだ「ととのう」という言葉も知らなかったので、身体が宙に浮いているような不思議な感覚と表現していました。 これを2クール体験(まさか2回も同じことをするなんて思っていませんでした)。2回目は代謝が良くなっているせいか、さらに熱く感じ、気力で乗り切ろうと必死に耐えました。 おかげで終了後は、真っ直ぐ歩けないほどフラフラに。私の知人は、クールダウンで池に飛び込んでいましたが、その時の私には勇気がありませんでした。今の私なら、躊躇なく飛び込んでいることでしょう。 この「ピルツ」を体験した翌日の身体はとても軽く、これまで経験したことがないくらいに肌の調子が良くなったことを今でも覚えています。 そして、今人気を集めている恵みの湯の「ハーブサウナ ハーブロウリュウ」は、まさにここが原点です。この経験がなければ、恵みの湯のハーブサウナはなかったかもしれません。 まだまだ改良の余地はありますが、今後もよいサウナを提供できるようにと常に考えています。 90℃を超える熱いサウナは苦手 こんなすごい体験をした私ですが、やはり熱すぎるサウナは苦手です。80℃前後の優しいサウナが好きです。 さらに、サウナ室では、必ずと言っていいほど下段に座ります。上段の熱いポジションに座られている方をみると、スゴイなぁと感心します。 でも、ここで私は真似をしません。つねに自分のペースを守ります。そして、サウナ室での滞在時間も自分のペースです。その日の体調や自分の気持ちの良いところを探ります。 自分よりも先に入っている人がいると、その人よりは後に出なくちゃ・・とか有名なサウナーさんの言っている入室時間は〇〇分だからもう少し我慢・・とかそんなことは気にする必要はありません。 また、サウナ室に入る回数も1回の時もあれば、2回の時もあります。ここもまた、自分ペース。その日の自分と向き合い、決して無理はしません。 3回繰り返す方が多いような気がしていますが私はロウリュウを組み入れることで2回の繰り返しで十分ととのいます。 私の一番心地よいルーティーンは、 1.バブルバスで身体をほどよく温める 2.1回目、高温サウナ 3.15~20分のクールダウン 4.2回目、ロウリュウサウナ それぞれの入室時間は、6分の時もあれば8分の時もある。その時の体調次第で決めています。 そして私は、クールダウンの時間を十分にとるようにしています。 これは、あくまで私のルーティーンなのでみなさんもご自身の身体と向き合いながら、自分の心地よいペースを作ってください。...

夏のお風呂に合うハーブ(野草)の紹介
前回、土用の丑の話(https://yuyu-sousou.com/blogs/column/20210723_doyouushiyu)で、丑湯に使うと良いハーブの話が出ましたが、それ以外にも夏の入浴にとても良いハーブ(野草)がたくさんあります。 夏は、強い紫外線による日焼け、お子さまの湿疹やあせも、虫刺されなど肌のトラブルが気になる時期。 そんな時は、ハーブのエキスでお湯を柔らかくして、肌への刺激を和らげましょう。今回は、そんな夏の肌ケアに良いと言われているハーブ(野草)をご紹介します。 ビワの葉 古くからインドでは、ビワの木のことを「大薬王樹(だいやくおうじゅ)」、ビワの葉のことを「無憂扇(むゆうせん)」とよび、病気を治して憂いを無くすものとして、ビワの薬効を生活に役立ててきました。また、中国では、「枇杷葉(びわよう)」とよび、貴重な生薬として利用してきました。 ビワの葉の採取は、一番薬効が高いと言われる1月の大寒ごろが良いと言われていますが、薬学博士の村上光太郎先生によれば、自家用に使用する際は、採取時期を気にしなくてよいとのことです。乾燥した葉を浴用に使用するほか、お茶として飲んだり、アルコールに浸けるチンキ作りにもおすすめのハーブです。 カキの葉 日本には奈良時代に渡ってきたとされるカキの葉。カキの葉は、レモンよりもビタミンCが豊富で、暑い夏の紫外線から身体を守ってくれます。6月から8月の暑い時期に採取した葉が一番ビタミンを多量に含んでいますが、採取後は時間とともにビタミンCが減少するので、早めに処理をしましょう。 カキの葉を2分程度蒸して酵素を分解させます。その後、手早く広げ熱を冷まし、しっかりと乾燥させます。ちなみに、入浴用として使用する場合は、甘ガキ・渋ガキのどちらでも良いです。また、9月を過ぎると、葉に渋み成分が増えますので、飲用として使用する際は注意が必要です。 シソの葉 食用として、たいへん馴染みのあるシソ。江戸時代からシソは重要な薬として使われていたことが「大和本草」(1709年刊行、貝原益軒により編纂された本草書)に書かれています。香り成分のペリルアルデヒドには強い防腐作用があり、食中毒予防として刺身のツマとしても利用されています。 また、夏にシソジュースを飲んでおくと、秋や春のアレルギー症状の緩和も期待できるそうです。浴用に使用する際は、茎も使用できます。葉茎を乾燥させたものを袋に入れ、お風呂に入れて楽しみます。 アカメガシワ 江戸時代から痔の媚薬として知られるアカメガシワ。新芽や新葉が赤い毛で覆われるところから名づけられました。成葉になると、赤色はなくなり、大きな葉になります。昔は、これを皿の代わりにして食べ物をのせたり、包んだりしていたそうです。 薬用として使用されるのは、葉と樹皮です。樹皮エキスを使った治療薬も市販されています。浴用には、枝葉を使用します。夏に採取して、水洗いし、細かく刻んでカラカラになるまで乾燥させます。お風呂に入れる際には、塩を一緒に入れると効果的だそうです。 ゲンノショウコ 「現の証拠」という意味を持ち、使用するとすぐに効果が表れることから名付けられました。また、地域によりその呼び方は様々で、イシャイラズ、タチマチグサ、テキメンソウなどがあります。 ゲンノショウコの薬効成分はタンニンで、その含有量は花も盛りとなる夏の土用丑のころが一番高いといわれています。採取した葉茎は、水洗いして日に当て、しっかりと乾燥させます。夏の肌のトラブルには、乾燥したものを鍋で煮だして濃く煎じ、浴槽に入れるとよいでしょう。ちなみに、今年、うちの農園で咲いた花は白花ばかりでした。(昨年は、赤白両方の花が咲きました) スイカズラ 日当たりの良い山地や野原などに普通にみられる常緑のつる性植物です。咲き始めの花は白色、もしくは乳紅色ですが、のちに黄色に変化することから、花の生薬名は「金銀花」と呼ばれています。一方、茎や葉は冬でも枯れないため、冬を忍んで青いままでいるという意味で「忍冬」という生薬名が付いています。和名の「スイカズラ」は、花の蜜を吸うと甘みがある、つる性の植物のことを表しています。 浴用として使用する際は、乾燥した葉茎50~100gくらいを袋に入れ、水から浴槽の中に入れて湯を沸かします。美容効果が期待できます。花は香りが良いため、ホワイトリカーなどアルコールにつけてスイカズラ酒にしたり、ハーブティーとして飲用したりするのもよいでしょう。 スギナ 全国各地、日当たりの良い場所に生える野草です。非常に生命力が強く、多量に生えてくるので、処理に追われる人も多いのではないでしょうか。春先にツクシ(胞子茎)を生じ、のちに緑色の麟葉(スギナ)となります。スギナは、高さ30~40センチほどに成長します。一見、葉のように見えますが、ほとんどが茎だそうです。 5月ごろに全草を採取して風通しの良い場所で乾燥させます。浴用として使用する際は、生のスギナを100~200gほど袋に入れて、水から浴槽に入れて沸かします。乾燥したものを使用する場合は半量にすると良いでしょう。 カキドオシ 以前、半谷さんに学ぶ「和ハーブを身近に感じる」(https://yuyu-sousou.com/blogs/column/20210618_waherbs)でも登場したカキドオシ。花の咲く4月~6月ごろに採取して、しっかり乾燥させます。ハーブティーにして飲むと優しい味でとても美味しいですが、浴用としても使用できます。 村上光太郎先生は「湿疹やあせも、皮膚の炎症がひどいときには、煎液(ハーブティー)を飲むばかりでなく、煎じた液(鍋で煮だした液)を風呂に入れて入浴すれば、かゆみも取れ、次第に治まります。生の葉のしぼり汁を塗布すれば、早い効果が得られます」とおっしゃっています。(薬草をたべる 薬学博士村上光太郎より)比較的育てやすい植物なので、ご自身で育ててみてはいかがでしょうか。 ここまで夏のお風呂に合うハーブを紹介してきましたが、夏の入浴についても少し触れたいと思います。 入浴後、「汗が流れ出た」「汗が止まらない」ということはありませんか? せっかくお風呂に入って、身体をキレイにしたのに、たくさん汗をかいてしまっては元も子もないです。...