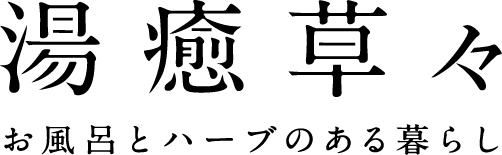読みもの

土と植物に癒される、家庭菜園を楽しもう
こちらのコラムでは、自分らしくナチュラルに暮らすためのポイントを、各務原の街の魅力と共にお伝えしています。 雨が多く、肌寒い日も続いていた4月。 ゴールデンウィークをあけると、一気に暖かくなり、新緑が眩しくなりますね。 思わず外に出たくなるこんな季節ですが、コロナ禍では旅行に行くのもなかなか難しい・・・。 そんな時はお庭やベランダで、野菜を育ててみませんか? 野菜の苗を買ってみよう 先日、野菜の苗や種を買いに、岐阜県各務原市にある「伊木山ガーデン」の園芸館に行ってきました。 伊木山ガーデン https://www.igiyamagarden.com/blank 東海地区最大級と言われるこちらの園芸館は、花や野菜の苗から観葉植物、鉢や土まで、おうちで植物を育てるためのものが全て揃っています。 今回は、ミニトマトやししとうなど夏に採れる野菜や、パセリやバジルなどの便利な薬味など、育てやすい苗を探しに行きました。 たくさんの苗に囲まれて、あれもこれも気になってきます・・・! ミニトマト一つとっても種類も様々。 そんな中から、皮が薄くて糖度が高いという「甘っこ」「千果」の2種類を買ってみました。 野菜は他にも、ししとうやオクラなど失敗しにくいものをチョイス。 庭からちょこちょこ摘んで使うのが便利なハーブや薬味は、毎年育てていてとても重宝しています。 トマトにも合うバジルはマスト! 放っておいてもぐんぐん育つし、香りがとっても良いので収穫が楽しみなハーブです。 他にも、大葉やパセリ、わけぎなどを買いました。 カゴの中にいろんな野菜が入るとワクワクしますよね。 春は野菜が育ちやすく、売り場にもたくさんの苗が溢れているので、この季節こそ家庭菜園にはぴったりです! 伊木山ガーデンには、野菜の苗以外にもたくさんのお花や観葉植物もあり、見ているだけでも楽しくて1〜2時間があっという間にすぎそうなのですが、今日は我慢。 家に帰ってすぐに苗を植え替えましょう! 畑やプランターに苗を植えよう 我が家には小さなお庭があるので、土を耕して野菜の苗を植えます。ハーブ類はプランターへ。 土を掘っているとダンゴムシやアリなどいろんな虫たちがやってきますが、ちょこまかと動き回ってかわいいなあと思います。 ポカポカとした日差しに少し汗をかきながら、時に風が吹いて気持ちの良い朝。...

こどもの日と端午の節句。母に感謝し、菖蒲湯で邪気を祓おう
5月5日はこどもの日。 こどもの日といえば、こいのぼりや五月人形を飾ったり、柏餅やちまきを食べる「男の子のお祭り」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。 お風呂屋さんの業界では、こどもの日といえばなんといっても「菖蒲湯」です。一般のご家庭では、なじみが薄いかもしれませんが、こどもの日の「菖蒲湯」は、冬至の「ゆず湯」と並ぶお風呂の一大イベントなのです。 「こどもが菖蒲湯に入ると元気に育つ」 「菖蒲が邪気を祓ってくれる」 など、さまざまな言い伝えのあるこのイベントですが、その意味や由来について、また、ハーブ湯としての菖蒲湯のメリットなどについて、ご紹介したいと思います。 「端午の節句」は男の子の節句 こどもの日が1948年、戦後に生まれたのに対して、端午の節句は「五節句」といって、奈良時代に中国から伝わった伝統行事です。ちなみに「端午」の「端」という字は初めという意味「午」という字は五に通じるということで、5月初めの5の日、すなわち5月5日を表しています。 日本に伝わった当初はまだ男の子の節句という意味合いはありませんでした。 江戸時代、幕府は端午の節句を大切な日として祝日と定め、菖蒲と尚武(武事・軍事を尊ぶこと)の音が一緒であることから、男の子を祝う祭事へと変わっていきました。 武家社会の間で鎧兜や武者人形などの「五月人形」を飾り、男の子の厄除けと立身出世を願うようになりました。やがて一般庶民の間でも広がり、武者人形や鯉のぼりを飾るようになり、端午の節句は、男の子が強く育つように祈りを込める日になりました。 これが現在も引き継がれて、5月5日が男の子の節句となったのです。 お風呂屋さんとしては、こどもの日の行事として、一般的にこいのぼりや柏餅と比べるとまだまだ知られていない「菖蒲湯」をもっと広げたいと思っています。 菖蒲で厄除けと男の子の成長を願う! 前述のとおり、古代中国では菖蒲の強い香りから「邪気を祓う」効果があるとされていました。 また、菖蒲酒にして飲んだり、葉や根を束ねてお風呂に入れる「菖蒲湯」に浸かるという風習が生まれました。 菖蒲の香りがもつ効果とは 菖蒲湯は、血液循環を促して身体を温め腰痛や神経痛をやわらげる効果があるとされています。また、香りによって心身のリラックス効果を得ることもできます。菖蒲の香りは強いですが、含まれる成分には刺激の強い成分は含まれません。そのため、赤ちゃんや肌の弱い方でも入浴可能と言われています。 菖蒲湯の効果をもっと高める方法 菖蒲の葉を10本程度束にして湯船に浮かべれば、菖蒲湯の完成です。でも、せっかくさまざまな効果が期待できるなら、できるだけその効果を高めたいですよね。 1.根付きの菖蒲を使用する 菖蒲湯には主に菖蒲の葉が利用されますが、根茎の方がより多く精油となる成分が含まれているため、香りやその効果、根付きの菖蒲を使用した方が強くなります。しかし、なかなか通常のスーパーでは手に入らないことが多いので、もし手に入れば、という方法になります。 2.お風呂の湯温を熱めにする お風呂はいつもより少し熱めに沸かした方が、菖蒲の香りや効果がより強く引き出されます。注意点としては、小さなお子さまや赤ちゃんも入浴する場合は、洗面器を使う以下の方法がおすすめです。 ①菖蒲の葉(根)を2㎝くらいに刻む ②刻んだ菖蒲をネットや不織布等に入れて洗面器に入れる ③洗面器に入れた菖蒲に熱湯を注ぎ、10分蒸らす ④菖蒲を洗面器のお湯ごとお風呂に入れる 3.菖蒲の葉や根は細かく刻む 菖蒲湯の写真などを見ると、菖蒲の葉を束にしてそのまま湯船に浮かべているものが多いのですが、菖蒲の葉や根をそのまま入れるのではなく、ハサミなどで細かく刻んでから熱湯で蒸らすことで、より成分が抽出されやすくなります。...

ハーブとスパイスの料理を使ったケアするカフェ -Medi Café さんを訪ねました- 後編
愛知県江南市のmedi Cafeさんフードコンサルタントのひらつかがお邪魔しました。前編は、お店やお料理の想いとハーブとスパイスの関わりについてでしたが、後編はお店の紹介とお料理についてです。 前編では、mediCafeオーナーの山田さんにお店をはじめようとしたキッカケやお店の想いなどについてお話をお聞きしました。 前編をご覧になっていない方はこちらからどうぞ↓↓↓ https://yuyu-sousou.com/blogs/column/20210326_column お子さんの学校行事やお休みに合わせて、お店の営業時間や定休日も変更になるそうです。「わがままなお店なので、、、」とオーナーの山田さんはおっしゃっていましたが、ご家族やご自身の時間を第一に考え、無理のない営業スタイルはお店のコンセプトと合っていて、素敵です。ということですので、お出かけの際はMediCafeさんのインスタグラム(@ medicafe.herb)等でご確認ください。 わたしがお邪魔したときは、ちょうどお昼時でたくさんのお客様で賑わっていました。みなさん会話が弾んで楽しそう。 お昼のメニューはこんな感じです。気まぐれランチとハーブ&スパイスカレーランチどちらかを選びます。キッズランチもあるのでお子さま連れも歓迎されていますね。 わたしは気まぐれランチを注文してみました。気まぐれという名前の通りメインは日替わりだそうです。オーナー山田さんのお父さんが作る自家製の野菜をたっぷりと使われたデリと共にドーンと出てきます。 お皿から溢れそう、、、 メインで使うお肉や魚もほぼ国産のもので・・とこだわっているそうです。野菜も自家製や地場のものを使っているからこそ、同じ野菜が続くこともあるそうですが、それも自然の摂理です。スパイスやハーブを使って味や見た目を変化させる工夫が施されています。 たっぷりすぎるお野菜で罪悪感がなく、どのお料理にもスパイスやハーブが使われているそうです。スパイスと聞くと辛い!と連想される方がいらっしゃいますが、スパイスは辛いものだけではなく酸味のあるものや甘味のあるものなど様々な味があります。しょうがやにんにくもスパイスの仲間ですので辛いだけではないんですよね。体を温める効果や免疫力を高めたり、食材を柔らかくするような作用があるものもあります。どのお料理もハーブやスパイスたちが主張しすぎずとても食べやすいです。 山田さん、、、さすがです!!! ハーブ&スパイスカレーはこんな感じです。 カレーは、その日の朝スパイスを調合するところからスタートするそうです。香りや味の奥行きが広がり、お店独自の個性の出るカレーもおすすめです。 さらにドリンクは、ハーバルセラピストの資格を持つオーナーのこだわりのブレンドハーブティー10種類の他、コーヒーなどが選べます。 少しでも若返りたいアラフォーのわたしは、若返りの青い美肌茶を選びました。 なんだかちょっと美白になって若返った気分がします。そして、デザートのスパイスケーキも、、、 食後にゆっくりとハーブティーを飲みながら過ごす至福のときです。とっても明るく気さくにお話されるオーナーの山田さんに会いにいらっしゃるお客様もたくさんいらっしゃるようです。 テイクアウトもされていますので、お家でゆっくりご家族とお料理を楽しむのもいいかもしれませんね。 こちらの情報は、2021年4月の情報です。メニューやお値段などは変更になることがあります。詳しくは、メディカフェさんのインスタグラムやWEBサイトをご覧くださいね。 MediCafe 愛知県江南市松竹町上野206−1公式サイト:https://medi-cafe.info/Instagram:@ medicafe.herb ライター情報ひらつかやよい フードビジネスコンサルタント 食と食をデザインするフードビジネスコンサルタント。株式会社 Coneru 代表 岐阜県大垣市を中心にシェアキッチンを運営。食を介した人の繋がりとシェアリングエコノミーについて研究。 note:https://note.com/coneru_nazokotwitter:https://twitter.com/yayoi_nazokocorporate:http://coneru.net/

ハーブとスパイスの料理を使ったケアするカフェ -Medi Café さんを訪ねました- 前編
愛知県江南市のショッピングモール隣、住宅の一角にある白い可愛らしいカフェ。2017年10月にハーブ&スパイスのカフェをオープンされて3年目を迎えます。 Medi Cafe オーナー山田真代さんにフードコンサルタントのひらつかが、お店作りやハーブとスパイスの料理へ想いをお聞きしました。今回、前編と後編に分かれてお届けします。前編は、お店やお料理の想いとハーブとスパイスの関わりについて、後編はお店の紹介についてです。 実は、2年くらい前だったかインスタで見つけてずっと追っていたんです。なかなか伺う機会がなかったのですが今回お会いできて嬉しいです。ハーブ&スパイスのカフェをしようと思ったキッカケはなんですか? 実は、私自身が精神的に病んで、引きこもっていた時期があったんです。その時にハーブティーを飲んだらすごく気持ちが楽になった経験から、なんかいいんじゃないかと思って、ハーブの勉強を始めました。 ハーブティーもとても良いけど、ご飯の中に取り入れる方が自然に食べられるし、カラダにとっても得をするというか…もっとカラダにいいよね。ということからお食事も楽しめるカフェにしたんです。 なので、オシャレなハーブカフェっていうよりも病んでる店主のハーブカフェというのがコンセプトでもあるんです(笑) おひとりさまとかお疲れの人の居場所となったらいいなと思って。家も嫌ってなったときに居場所って意外となくて。 わたしが病んでた時期、賑やかなカフェにはハッピーな人がいっぱいいて辛いし、私自身もひとりでショッピングモールの隅っこで泣いてたことがあったんですね。だから、お店の作りもカウンター席を多めにしたりしているんです。 おひとりで来られてちょっと元気のない人とかとお話しされたりもするんですか。 そうですね、心のバランスを取ってくれるようなハーブティーをおすすめしたりしています。薬飲んだり、心療内科行ったりとか…私自身が経験あるので、人には言えないお悩みにも寄り添えるかなと思います。 SNSでもご自身の経験を赤裸々にお話しもされたりするんですね。 そうなんです(笑)。お店の運営としては賛否両論あると思うのですが、心身のお辛い方がなかなか自分から心療内科に行ってるとは、言えないと思うんですよね。なので、自分の経験を発信して、気楽に来てもらってお話ししやすいようにしたいな…と思ってるんです。誰もがハッピーな状態ばかりではないし、疲れちゃうことなんてみんなあるんですよね。 そうですよね、お料理もハーブとスパイスがテーマということですが何か気をつけていることとかありますか。 ハーブもスパイスもですが、苦手意識が多い方がいらっしゃるんですけど、生姜とかニンニクだってスパイスだし、料理の中に自然に摂り入れるようなことをつねに考えています。 「使っているけど食べれるでしょ」っていう感じで、ここで食べたことで苦手意識を克服するキッカケになったらいいなと思います。 ハーブもスパイスも食材にいろんな作用があると思いますが、調理方法としてどのような活用をされていますか。 だいたいのお料理にハーブ入れているんですけど、味は主張しないけど実は入っていたりとか、風味付けとか色を付けるとか。調味料を使わなくてハーブでいけるのであれば、ハーブを使うとか。 例えば酸味を出したい時には、ハイビスカスとかコクを出すなら根っこ系のハーブを使うとか。出来るだけハーブやスパイスを使って風味を出すような工夫をしていますね。 食材のこだわりはありますか。 メインで使うお肉やお魚は国産に拘っています。野菜は自家製で、実家の父に協力してもらって作ってもらっています。私も日曜には必ず岐阜の畑へ行って収穫や、世話をしに行っています。自家製の野菜で間に合わないときは購入もしますが、その時も出来るだけ地元野菜を仕入れるようにしています。 自家製や地元野菜となると旬のものになりますね。季節によっては同じ野菜が続いたりとかもしますよね。 そうなんです。白菜ばかりとかキュウリが続くとか、今は大根が山盛りです(笑)。これも調理方法やスパイスで変化を出しています。そうすると、お客さんからこれどうやってやるのと聞かれたり、逆に教えてもらったりして会話が生まれたり、料理のバリエーションの幅も広がるので、それもいいのかなと思っています。 メニューが日替わりカレーとか気まぐれランチとありますが、スパイスの調合とか大変じゃないですか? 同じ味にするのが苦手なんです(笑)その日によってムラがありますし、いつも同じだと私自身が飽きてしまうし、いろいろやりたい気持ちも出てくるので日々実験です。...

一年中楽しめる!一番身近な和ハーブ「ヨモギ」
身近な和ハーブの代表として、一番に思い浮かぶヨモギ。 食べてよし、飲んでよし、浸かってよし、塗ってよし、嗅いでよし、燃やしてよしの5拍子揃ったハーブです。ヨモギには様々な種類があり、一年を通して様々な形で使うことができます。今回は、ヨモギの見分けかたと使い方をご紹介します。 春には、白っぽい緑色の若葉が出始めるヨモギ。 ヨモギはキク科のヨモギ属。ヨモギの仲間は日本に30種類以上あります。一般的によもぎ餅やお茶などで使われるヨモギは「カズサヨモギ」と呼ばれるものです。 ほかにもお灸の艾(もぐさ)にするものは「オオヨモギ」。 沖縄で“フーチバー”と呼ばれ、沖縄のスーパーや市場でも購入できる「ニシヨモギ」があります。 沖縄では、ジューシー(炊き込みご飯)やヤギ汁などにも使用されています。私はニシヨモギの雑炊をいただいたことがあります。香りがよく、苦みも少なくて、とても食べやすいヨモギでした。 また河原や海岸の砂地に生える「カワラヨモギ」の乾燥した花穂は茵蔯蒿(いんちんこう)という名の生薬として漢方薬にも使われています。 そして、ハーブの世界で「マグワート」と呼ばれているのは「オウシュウヨモギ」のことを言います。 私たちに一番身近な「カズサヨモギ」 ・カズサヨモギの見分け方 ・ヨモギの効果 ・ヨモギの使い方 ヨモギの香りはするか? 野草を見分ける時にとても大切なのが“香り”。 食べる野草を摘む時に目だけで判断するのは危険なことがあります。ヨモギの若葉は、猛毒トリカブトと似ているといわれていますが、トリカブトにはヨモギの香りはしません。 ヨモギの葉を摘んだら、ヨモギの香りがするか、必ず揉んで香りを確認してみましょう! 葉の裏に白い毛は生えているか? ヨモギの葉の裏には必ず、お灸のモグサ(艾)の材料になる白い毛が生えているので、目と触感でチェックしましょう。 托葉はついているか? ヨモギは葉の付け根に“仮托葉”(たくよう)という小さな葉がつくのも特徴です。若葉の時しか見分けがつかないという方は、仮托葉を確認してみてください。 ヨモギの効果 クロロフィルやタンニンのほか、有効成分の宝庫のヨモギは乾燥したものだけではなく、生葉も大変優れています。指を切って、血が止まらない時に揉んでつけたら血が止まったことや、私の講座に参加されていたお子さんが腕を毛虫に刺されて発疹が出た時に生葉を揉んでつけて、手ぬぐいで巻いておいたら15分ぐらいで落ち着いたことがありました。 一般的な効能としては、生葉を揉んで貼ると、止血のほかにも虫刺され、切り傷、打撲傷や腫物。煎じて飲むと強壮、健胃、去痰、止血、腹痛、風邪、食中毒、冷え性などほかにも色々な効能があるといわれています。浴湯料としては、あせも、冷え性、腰痛、リウマチ、美容などにもよいそうです。(出典「食べる薬草事典 春夏秋冬・身近な草木75種」村上光太郎 著)...

ストレス や 心のモヤモヤ 春へと向かうわたしたちの心身を整える ハーブ
人類は進化していく過程で、常に植物の力を借りてきました。古くは民衆の心をしずめるために、さらには病める人の治療薬として、また食卓を豊かにする調味料や保存のための殺菌剤としての役割も果たしてきました。 近代になり科学が進歩し、薬をはじめ、ありとあらゆるものが合成可能となった社会では、人は植物との結びつきを忘れたかのように暮らしていますが、人は植物なしでは生きていくことができません。 いつの時代も人に力を与え、疲れを癒してくれるのは植物を含む大自然、そこに近い場所にいるほど健康に近づくと考えられますが、都市部でそれはなかなか難しいですよね。 植物を身近に生活することが難しい方は、部屋に1鉢植物を置いてみましょう。小さなもので構いません。 日々の中に生じるちょっとしたイライラやモヤモヤは、心身に思った以上の負荷を与えています。1日の終わりに心とからだの様子を眺め、違和感を持つ部分があったら早めのケアを。植物の力を借りて、整えていきましょう。 からだへと関心を向ける 折しも2月の立春からは暦上では春とされ、四季の立ち上がりを迎えています。草木の芽吹きと同様に、冬の間、停滞気味になっていたわたしたち人の細胞も少しずつ活発になっていきます。 その動こうとする力に身体が対応しきれていない時に起こるのが、めまい、無気力、不安感、不眠などの自律神経系にまつわる不調です。例年2~3月の体調について思い当たる方もあるのではないでしょうか。 ロシアのスポーツ選手や宇宙飛行士が体力維持のために飲用していたことで知られる「エゾウコギ」というハーブは、別名シベリア人参とも呼ばれ、神経系、免疫系、ホルモン系などあらゆる機能を高め(=アダプトゲン作用)、この時季の体調管理や感染症の予防にも役立ちます。他に風味の良いハーブティーとして近年人気のホーリーバジルにも同様の働きがみられます、これらを活用してみて下さい。 エゾウコギ 科名:ウコギ科 使用部位:根、根茎、茎 活用法:ハーブティー(ドライハーブ2~3gに熱湯を注ぎ、5~10分蒸らす)チンキ剤にしても 花粉症へと対応するハーブ 日本気象協会によると2021年の花粉飛散量について、九州から関東おいては前シーズンより多いとの予測がされています。 鼻がぐずぐずする時にスッキリするハーブは、エルダーフラワー、ルイボス、ペパーミント、ネトルなどいくつか挙げられますが、その中でもオススメなのがペパーミントです。 お湯を注いでティーにすると、スッとした香りが蒸気と共に立ち上り、辛い鼻のぐずぐずがいくらか楽に感じられます。また爽やかな香りは気分もスッキリさせ、実は優秀なメディカルハーブとも言われています。 栽培も簡単ですので、一家に1苗、常備されるといいのではないでしょうか。ミント類には様々な種類がありますが、ペパーミントがおすすめです。苗をお求めの際は、間違いのないようにして下さい。 ペパーミント 科名:シソ科 使用部位:葉使用法:ハーブティー ハーブ2~3gに対し熱湯150mlで5分抽出。チンキ剤 ペパーミントの抽出には度数40%以上のアルコールが望ましい。 飲用の他、マウスウォッシュとしても活用できる。 栽培: 強い乾燥が苦手、プランター栽培時は水切れに注意する。 収穫: 若い葉を摘み取る。(蕾や花をつける頃は風味も効能も劣ります) 最後に一言… 人に本来備わっている健康や美しさを引き出すのは、日々の積み重ね 良い習慣を身につけ、心地よく生きていきましょう。 水野さと美 シュクレ メディシナルハーブ主宰...