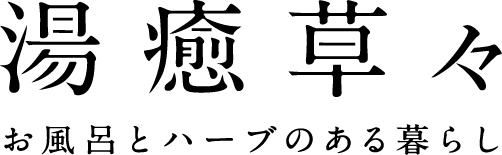読みもの

野草研究家・山下智道さんと巡る、各務原のハーブ旅【内藤記念くすり博物館編】
野草研究家の山下智道さんと一緒に岐阜県各務原市をめぐるシリーズ。 前編では「恵みの湯」さんを訪れた様子をお伝えしました。 https://yuyu-sousou.com/blogs/column/20220610_herbprince1 後編は、各務原市にある薬草ハーブを中心とした植物園「内藤記念くすり博物館」さんへ伺ったレポートです。 <目の前に広がる、広大な薬草畑> 内藤記念くすり博物館は、エーザイ株式会社が運営する国内初のくすり資料館。 展示館にはくすりに関する所蔵品や収蔵図書が2000点ほど展示され、医学・薬学の歴史や、くすりの正しい使い方について、社会に広めるための活動をされています。 さらに展示館の前には、広大な薬草植物園が広がっています。 野草研究家の山下さんは・・・さっそく、気になった植物を見つけて大興奮! 次々と写真をとりながら、わたしたちにも植物の特徴をレクチャしてくださいます。 淡いベージュの花びらの中心が黒くなっている、ちょっと不思議な雰囲気のあるこの花。ナス科の「ヒヨス」という植物で、幻覚などを引き起こす毒草です。 初っ端から物騒な植物を紹介してしまいましたが(笑)、魔女が用いたとも言われるようにメルヘンチックな側面もあります。 続いてこちらは、クソニンジン。今度はとんでもない名前ですが(笑)、ニンジンの葉に似たヨモギの仲間だそう。 美しい繊細な葉は独特な香りがします。中国では解熱に利用されていたとか。 とても珍しい植物ですよ!と山下さん。 博物館のスタッフさんに許可を得て葉を一枚取らせてもらい、丁寧に撮影をされていました。 山下さんは植物標本を作るために、珍しい植物や探していた薬草などに出会うとホワイトボードに葉を丁寧に広げ、写真として残しているそうです。 植物の美しい姿がそのまま残るのは素敵ですよね。私もやってみたくなりました! <温室で出会う、珍しい植物たち> 屋外の薬草植物園を歩き回った後は、温室へ。 暑い国が原産の植物は独特で初めて見るものも多く、参加者みんなで大興奮でした。 写真右の植物は「バニラ」です。 みなさんご存じ、アイスクリームやプリンに使うバニラビーンズがなる蔓性の植物。 ほんのりバニラの良い香りがします。 こちらはみなさん、、、なんの実かわかりますか?みなさんもきっと大好きな、チョコレートの原料になるカカオの実です。 私は初めて実物を見たのですが、すごく大きい〜!と思いました。ラグビーボールのような形、サイズ感で、ずっしりしています。...
薬草・ハーブ湯の楽しみ方
薬草 ハーブをお風呂に入れてみよう 01.薬草・ハーブ湯のお風呂を楽しむ 不織布に入ったまま1包をお風呂の沸かしはじめと同時に浴槽に入れ、湯に十分浸るようにします。沸いたあと、少し揉み浸し15分くらい湯になじませてから入浴します。 02.ハーブエキスを十分に引き出す方法 あらかじめ、鍋などで湯を沸騰させます。その中へ草木花のお風呂1包を入れ、じっくり煮出してから煮汁と一緒に湯船に投入します。熱めのお湯の方がハーブのエキスが出やすいですが入浴の際は、お湯を適温(40℃前後)に冷ましてから入浴します。 詳しくはこちら>> 03.アレンジして楽しむ 香りが足りない場合は、ソルトにお好きなエッセンシャルオイル(精油)を2~3滴ほど垂らし、良く混ぜなじませます。不織布などに、お好きなハーブと香りのついたソルトを入れ、浴湯に入れてください。 使用後のハーブの活用法 使用後の草木花ハーブを再利用してみましょう。 上手な乾かし方 新聞紙やざるなどの上にハーブを広げ、風通しの良いところに置き、1〜2日ほど陰干しで自然乾燥してください。 乾燥したハーブの再利用法 よく乾かしたハーブの袋をそのまま靴や靴箱の消臭剤として。布のきんちゃく袋などに入れサシェとして、クロゼットやかばんに入れて。枕元に置いて、入眠前のリラックスに。 そのまま土に戻すこともできますが、コンポストを利用し、肥料として再活用もできます。 乾いたハーブを袋から取り出し、玄関に撒き、掃き掃除に使用するとほこりをじょうずに巻き込み、ほのかな香りも感じられます。 薬草 ハーブのお風呂 Q&A はこちら>>>

野草研究家・山下智道さんと巡る、各務原のハーブ旅【恵みの湯編】
野草研究家の山下智道さんをご存じですか? 野草教室や植生調査のため世界各地を飛び回り、ハーブを使った料理やコスメのプロデュースもされたりなど、野草やハーブの分野で活躍されている若手の野草研究家さんです。 そんな山下さんが、岐阜県各務原市の銭湯「恵みの湯」にいらっしゃるということで、私も同行させていただきました。 <恵みの湯をじっくり見学> 恵みの湯は株式会社日本温浴研究所が手掛ける、薬草ハーブとサウナが自慢のお風呂屋さん。薬草ハーブたっぷりの薬草湯は、季節ごとに変化があり来るたびに楽しめます。 また、自社の農園で栽培されたハーブをフレッシュなまま使ったハーブロウリュウのあるサウナは、日本全国からお客様がいらっしゃるほどの人気。 そんな「ハーブ推し」の恵みの湯で、山下さんは興味深そうに施設を見学されていました。 「本日のハーブ」が飾ってあるお風呂の入り口から、「いいですね〜!」を連発する山下さん。 お風呂とハーブについてスタッフとお互いに情報交換しながら、まだ序盤なのにこの熱量?とびっくりしました。笑 この日は臨時休業だったため、男湯女湯どちらも見せてもらうことができました。 露天風呂にはお庭があり、そこでもさっそく植物のチェックを。「お風呂でも使えるしお茶にもできるような植物もありますね、さすがです!」など、話が弾みます。 日本温浴研究所では、オリジナルブランドの入浴剤も開発しています。 恵みの湯でも販売する、上質なドライハーブを贅沢に使ったギフト向け入浴剤「ルゥルディマン」や、好きなハーブを選んで自分でブレンドしてお風呂に入れるシングルハーブのシリーズ「YUNIHA」など、とても興味深くご覧いただいていました。 「贈り物でもいいし・・・自分でも使ってみたい!」ということで、恵みの湯から山下さんにハーブ入浴剤「草木花のお風呂」などをプレゼント。 <ハーブの加工工場へ> そのあとは、ハーブの加工工場や研究室の見学へ。 日本温浴研究所はお風呂の運営だけでなく、ハーブの入浴剤を作るための農園から工場、研究室まで完備しています。 ハーブを育て、ハーブを乾燥・粉砕したりなどの加工をし、入浴剤にするための研究や試験を経て、包装されて商品になるまで、工場で一貫して生産できるような体制を現在整えているとのこと。 濾過装置や乾燥機などを見ながら「これ欲しい〜!」とワクワクしている山下さんと、説明に熱が入るスタッフの並河さん。 好きなものが一致すると、話は尽きないですよね。 <新しい施設でハーブイベントの打ち合わせ> 恵みの湯のすぐ横で、現在建設中の施設も見学しました。こちらは、日本温浴研究所が運営するオンラインストア「湯癒草々」のリアルな体験場所として、ハーブを育てるハウスやガーデン、加工工場などを兼ね備えた施設になる予定。 と言っても、単なる製造場所ではなく、ハーブを実際に収穫をしたり、ハーブを使った体験もできる、ハーブ好きさんの憩いの場所としても利用できるようになります。 秋にオープン予定のこちらの施設では、オープンイベントとして山下さんと一緒にハーブを楽しめる企画も計画中です。実は今回の恵みの湯訪問は、このイベントの打ち合わせも兼ねたものでした。どんなイベントになるか、楽しみですね。 <道端の草にも一つ一つ名前がある>...

入浴後の乾燥しやすい肌に潤いを
連日、気温の高い日が続いています。肌が焼けるような痛さを感じることも増えてきました。紫外線の強い日は肌へのケアが欠かせません。今回は強い紫外線や乾燥から肌を守るための方法をご紹介します。 ~目次~〇入浴と保湿1.入浴でこもった熱を排出2.入浴後の保湿〇After Body Treatment1.シンプルで優しい素材2.実際に使ってみて〇最後に 入浴と保湿 1 入浴でこもった熱を排出 暑い日は、シャワーで汗を流すだけという方も多いと思いますが、熱くなり始めた時期は、暑さに慣れておらず、入浴することで体にこもった熱を排出する効果も期待できると言われています。激しい運動を15分程度行うことでも発汗することはできますが、入浴の方が手軽ですね。 さらに世界中に温泉やサウナの施設はありますが、毎日のように湯船につかる習慣のある国は日本のみといっても過言ではありません。この入浴習慣が健康寿命を延ばすという研究結果も出ています。毎日入浴して健康づくりに役立てていきましょう。 2 入浴後の保湿 入浴後は皮膚が乾燥しやすいタイミングです。入浴後に乾燥する理由は2つあります。1つ目はお風呂につかることにより、皮膚表面の皮脂が取り除かれ、皮膚の保湿成分であるセラミドがお湯に溶け出すためです。2つ目は温まった皮膚が冷えていくときに水分が蒸発するためです。この2つの理由から入浴後は乾燥しやすいタイミングになっています。皮膚が乾燥するとシワやシミにもつながります。入浴後は保湿をして健康肌を守りましょう。 保湿のタイミングはお風呂あがり10分以内に。10分を過ぎると急激に乾燥が進むという研究結果もあります。10分以内に保湿することが理想ですが時間がないという方も多いのではないでしょうか。身体が冷える前にサッと短時間で保湿できるアイテムがあれば嬉しいですよね。(参考:最高の入浴法 温泉療法専門医 早坂俊哉著) After Bath Treatment 1 シンプルで優しい素材 12種類もの植物成分を調合している、ルウルディマンオリジナル商品です。肌が弱い方やお子様でも安心してご使用いただけるよう、ナチュラルな素材で仕上げています。肌に直接触れるものだから、優しい素材であることはうれしいですね。 調合されている成分の中で特に注目したいのは、国産のブルーローズです。ブルーローズは、紫色に近い色をした珍しいバラです。香りを保たせ育てることはとても難しいといわれています。 ブルーローズのエキスを含む本商品は、バラ調のやさしい香りをお楽しみいただけます。お風呂上がりの時間保湿時間が楽しくなりますよ。このトリートメント1本あれば短時間で手軽に保湿することができます。 入浴後は、After Bath Treatmentで保湿をして、お肌に潤いを…あなたの新しい習慣にしてみませんか。 2 実際に使ってみて 入浴後に全身に使用しました。濡れたままの肌に使うことができるので、保湿することが面倒だと感じていた私でも簡単に保湿することができました。トリートメントののびがよく、肌に浸透していくことを感じることができます。強すぎず優しい香りがお気に入りです。小学生の妹が使用しても肌などに問題はなく、香りも気に入っていました。こどものうちから入浴と保湿をセットで習慣にしておくと健康維持にもつながりますよ。After Bath Treatmentをきっかけに入浴と保湿の習慣ができるといいですね。 また、べたつきが少ないので入浴後だけでなく、ハンドクリームとして持ち歩くこともおすすめです。お出かけの時の気分転換にもなりますよ。アロマモイストなど入浴剤とセットでお使い頂けば贅沢なバスタイムにすることができます。 最後に 実際に使用して、お世話になっている方や大切な方に贈れば喜ばれること間違いなしの商品だと感じたので、湯癒草々の素敵なラッピングでAfter Bath Treatmentを誕生日プレゼントとして贈ったところ、とても喜んでもらえました。湯癒草々ではラッピングサービスも行っておりますので、気になった方はお気軽にご相談くださいね。ほかの商品も併せてぜひチェックしてみていただけると嬉しいです。...

心にも身体にも優しいハーブ「カモミール」
カモミールとは カモミールは世界中で親しまれているハーブのひとつ。りんごのような甘い香りに癒される方も多いと思います。 ヨーロッパでは「マザーハーブ(母の薬草)」とも呼ばれ、イギリスの童話「ピーターラビット」の中では、興奮して寝付けないピーターに、お母さんがカミツレ草(カモミール)のお茶を飲ませるシーンが描かれています。カモミールはとても優しいハーブなので、お子さまから高齢の方まで幅広く活用できます。 カモミールはヨーロッパ原産ですが、今では世界中のいたるところで栽培されています。岐阜県大垣市もカモミールの産地として有名です。 花の香りがリンゴに似ていることからギリシャ語で「地上にあるリンゴ」という意味の「カミツレ」と名付けられました。 日本に入ってきたのは、江戸時代末期。当時、幕府がオランダより60種類ほどの薬草を取り寄せている記録が残っており、その中にカモミールも含まれていたようです。 日本で栽培されはじめたのは明治の初めごろで、明治19年に制定された「日本漢方薬局」には「カミルレ」として記載されています。 カモミールには様々な種類がありますが、メディカルハーブとして利用されるものは2種類。ジャーマンカモミールとローマンカモミールです。 ジャーマンカモミール キク科の1年草で、太陽に向かって上に伸びます。小さく可愛い花は見ているだけでも癒されますが、りんごのような甘い香りはリラックスな気分をもたらしてくれます。フレッシュ、ドライともに、ハーブティーとして、また天然の入浴剤としても活躍します。 ローマンカモミール キク科の多年草で、横に這うように育ちます。踏みつけにも強く、香りの芝と表現されることもあります。 ジャーマンと同じ白い花が咲きますが、花のサイズはジャーマンよりも少し大きめ。花の数はジャーマンよりも少なめです。ローマンカモミールは、花だけでなく葉や茎にも香りがあるため、全草を使用します。ハーブティーにすると苦みを感じるため、アロマテラピーで使用する方が多いようです。 カモミールの私たちにとっていいこと カモミールは古くから薬として知られ、エジプトではマラリアの薬として使われていました。イギリスでは薬用として栽培され、ハーブティーにして服用し、発汗・解熱・健胃・強壮など、家庭薬として利用されていました。 日本では、明治3年に出された「和漢薬用植物」にカミツレ花として、「採暖・発汗・駆風薬とする、浴湯として多量使用される」と記載されており、薬用として使用されたことが残されています。 カモミールの主な作用は、心を穏やかにさせるとともに、チクチクしたお腹の調子や眠れない夜などによいとされています。また、手足の冷たさや女性特有のカラダの不調などにも用いられます。(参照:メディカルハーブ協会ハーバルセラピストコース・ハーブ各論) カモミールはキク科の植物です。ブタクサなどキク科のアレルギーをお持ちの方はご注意ください。 カモミールの育て方 比較的育てやすく、種まきからでもチャレンジしやすいハーブです。種まきは、春か秋にしますが、秋まきの方がしっかりとした苗に育ちます。種はとても軽いので、まいた後は軽く土をかぶせます。 植つけ地植えでもプランターでもどちらでも育てられます。日当たりの良い場所を好みますが、暑さには弱いため、直射日光の当たらない場所を選ぶとよいでしょう。また、用土は、市販のハーブ用か水はけのよい培養土を選ぶとよいでしょう。 管理土の表面が乾いてきたら水をたっぷりと与えます。プランターでの栽培は、乾燥しすぎない程度に水はけを良くすることが大切です。肥料は、与えすぎると香りがなくなるため、控えめにした方がよいそうです。元肥だけでも十分に育ちます。開花は4月~6月ごろ。こまめに花を摘み取ると、花の開花期間が長くなり、たくさん楽しむことができます。収穫は、午前中の時間帯が望ましいです。開花後、花びらが反り返る前に収穫しましょう。 アブラムシが付きやすいので、雨が続く場合や湿りやすい状態には要注意です。その際は、枝葉を適度に間引くなどして、風通しを良くするとよいでしょう。また、チッソが多い肥料を与えるとアブラムシが付きやすくなりますので注意しましょう。 ローマンカモミールの夏越し、冬越し梅雨から夏場にかけて蒸れて株元が痛みがちなので、梅雨前に刈り込んでおくとよいでしょう。耐寒性があるため、特に冬越しの作業はありません。しかしながら、次の開花に向けて、冬の間に刈り込んでおく、大きくなった株は株分けする、鉢替えなどの備えがあるとよいでしょう。 カモミールの活用法 ハーブティー 一番のおすすめは、ハーブティーです。開花の季節には、ぜひフレッシュカモミールティーを楽しみたいですね。 ジャーマンカモミールだけでも美味しいのですが、ジャーマンカモミールに少しのミント、セージを入れるブレンドで爽やかなハーブティーになります。また、ドライハーブを使用する場合は、カモミールミルクティーにするのも美味しいです。 ジャーマンカモミールミルクティーの作り方 ・ドライカモミール 3~4g程度(ティーバックの場合は2袋)・お湯 100~150ml・牛乳(豆乳でも)300ml・はちみつ(お好みで)・シナモンパウダー(お好みで) ...

4月~5月が旬の和ハーブ~カキドオシ&スギナ~
春爛漫の季節!自然の中にでかけて、野草を摘んでみたいなと思う方も多いかもしれません。 今回は、そんな時におすすめの和ハーブを2つご紹介させていただきたいと思います。 1つ目は香りがよく、和ハーブらしい野草「カキドオシ」を、2つ目はご存じの方も多く、雑草として苦労されている方もいるかもしれない「スギナ」です。 カキドオシとは? 漢字で書くと「垣通し」。シソ科の多年草で、日本全土の日の当たる路傍や山野に自生しています。乾燥が好きではないので、適度に湿った土地や半日陰でよく育っているのを見かけることが多いです。 生薬名をレンセンソウ「連銭草」といい、民間薬として日本では昔から糖尿病や腎臓病に使われてきたようですが、別名「カントリソウ(癇取草)」といわれるように、こどもの疳の虫にもよいといわれています。最近では、血糖降下作用があることがわかり、注目されている薬草です。 ヨーロッパでも古くから民間薬として使われていたそうで、日本では斑入りの葉の種類が「グレコマ」として園芸品種として売られているのをご覧になった方もいるかもしれません。 カキドオシの特徴・見分け方 1.葉や茎を切って、香りを確認しましょう!洋ハーブのような香りがします。 2.茎を触ってみましょう!シソ科らしく、茎の断面が四角なので、指で触っても四角が感じられます。 3.花がつく頃は5~20cmほどの高さに直立しますが、「垣通し」の名がついたように、徐々につる状になって、垣根を通すぐらい、地をはいながら伸びます。 4.対生した葉の縁は波型に浅い鋸歯があり、柔らかく、しわがあって毛が生えています。丸い葉が連続してついている様子が生薬名の「連銭草」の由来になったそうです。 5.4月に咲く花の色は薄い紫から淡紅紫色で、唇形。萼は筒状なのが特徴のかわいらしい花です。 カキドオシの活用方法 採取時季は葉や茎が硬すぎない、4~5月がよいですが、生えている時季ならいつでも収穫できます。カキドオシは香りがよいので、お茶や食べるだけでなく、様々な活用方法があるので、興味のあるものからお試しください。 ・お茶カキドオシの薬効をとりいれやすく、手軽に香りを楽しむなら、やっぱりお茶。さっと洗って、フレッシュのままお湯を注げば、香り豊かなフレッシュティーに!生のカキドオシを柑橘類のスライスなどと一緒に水に入れ、数時間おけば、さわやかなデトックスウォーターの出来上がり!洗ってから日陰干しで、乾燥させたものを保存しておけば、いつでもお茶として楽しめます。 ・お料理カキドオシは西洋ハーブのような香りがあるので、洋食にぴったり!フレッシュでも熱を加えてもバジルのように使うと、美味しくいただくことができます。特にペペロンチーノ、ジェノベーゼ風ペースト、ハーブバター、ハーブチーズ、天ぷらなどがおすすめ。魚料理や肉料理のつけあわせにしても、ポイントになりかわいく、香りもよいです。 ・入浴剤日々の疲れやリラックスもできるといわれています。 ・アイピロー前回、ご紹介した「アイピロー」(目の疲れにぴったり!和ハーブ香るアイピロー – 湯癒草々 -お風呂とハーブのある暮らし- (yuyu-sousou.com))の記事でも紹介させていただいたように、乾燥したカキドオシの香りや薬効を活かして、アイピローに入れるハーブとしてご利用いただけます。 スギナとは? 漢字で書くと「杉菜」。夏緑性シダ植物でトクサ科の多年草。ご存じのとおり、日本各地あちこちに生えています。日本だけでなく、北半球の暖温地域に広く分布しているそうで、私もスイスで見たことがあります。スギナはどなたでもご存じかと思っていましたが、講座をしていると20人に1人ぐらいはスギナを見たことがない方もいらっしゃいます。どこにでもありそうですが、都会ではスギナは見かけないので、知らない方がいてもおかしくないですね・・・。 生薬名はモンケイ「問荊」といい、利尿作用などがあると言われており民間薬として使われてきたようです。“雑草”として困った草だと思われている方は特に驚かれるのですが、近年はミネラルの豊富さや、水溶性ケイ素も注目されており、お茶はもちろん、美容にもよいサプリとしても販売されています。 カルシウムはほうれん草の155倍、リン・カリウムは5倍、マグネシウムは3倍ともいわれています。その姿形から、英名では「ホーステイル」と呼ばれ、ハーブとして扱われているので、「ホーステイルティー」としても売られています。 ツクシとの関係 前の年、スギナがつくった栄養分がでんぷんとなって、くきが変化した地下茎(ちかけい)にたくわえられています。この地下茎の栄養を使って出てくるのが、ツクシやスギナです。 栄養茎をスギナ(杉菜)、胞子茎はツクシ(土筆)と呼ばれます。地面に落ちた胞子から芽が出て、「前葉体(ぜんようたい)」といい、小さなコケのような植物になります。この前葉体のオスとメスの卵と精子が受精して、生まれた子どもがスギナとして育ちます。...